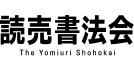お知らせ
東北展が開幕 表彰式・祝賀懇親会も開催
第36回読売書法展の東北展が30日、山形市の山形美術館と山形県芸文美術館で開幕しました。
書法会幹部役員や東北地区役員の作品のほか、東北6県の入賞・入選作品など計921点が展示されています。会期は11月3日まで。

山形美術館の会場

山形県芸文美術館の展示風景
また、同日正午から山形グランドホテルで表彰式・祝賀懇親会も開かれました。

第36回展事務長の高木厚人先生による審査報告

花束を贈られる読売俊英賞の皆さん

受賞者を代表して挨拶を述べる読売新聞社賞の馬上(もうえ)溪花先生

東北展実行委員長の石澤桐雨先生による閉会あいさつ
2019年10月30日(水)16:28
四国展 表彰式・祝賀懇親会を開催

読売俊英賞の皆さん
第36回読売書法展の四国展は最終日の20日、高松市内のホテルで表彰式と祝賀懇親会が行われ、読売俊英賞をはじめ入選・入賞した皆さんをお祝いしました。
読売俊英賞の受賞者は花束を手に一人ずつステージ上で挨拶し、大きな拍手を送られました。

審査経過を報告する第36回展総務部長の土橋靖子先生

事務長の高木厚人先生による乾杯の挨拶

四国展実行委員長の森上洋光先生による閉会挨拶
2019年10月20日(日)12:48
四国展を開催中

第36回読売書法展の四国展が18日から高松市のサンメッセ香川で開かれています。20日まで。

19日午後には恒例の親子書道教室も開かれました。

JR高松駅から会場まで、無料シャトルバスが運行されています。
2019年10月19日(土)16:36
東京展_席上揮毫・篆刻会のダイジェスト動画を公開中
8月25日に東京展の第1会場(国立新美術館)で行われた36回展「席上揮毫・篆刻会」のダイジェスト映像を本ホームページ上に公開しました。
トップ画面の画像を左右にスライドすると、実演された3人の読売書法会常任理事の写真が出てきますので、画面を直接クリックして動画をお楽しみください。
メニューの「動画」から、過去のダイジェスト映像も視聴できますのであわせてご覧ください。
2019年10月11日(金)12:00
「井茂圭洞展」_12日ギャラリートーク中止
銀座・和光本館で開催中の「書業六十五年記念 井茂圭洞展」の12日午後2時に予定していたギャラリートークですが、台風19号の上陸予報のため、中止することが決まりました。
展覧会の開催などお問い合わせは、和光(03-3562-2111)まで。
2019年10月11日(金)11:52
「浅見錦龍展」成田山書道美術館で開催中

㊨「入一覺」 平成18年(2006年)
日展や読売書法展で活躍し、2015年に92歳で死去した浅見錦龍先生の回顧展が、成田山書道美術館(千葉県成田市)で10月20日まで開かれています。日展出品作、毎日書道展準大賞作をはじめ、良寛詩や蘭亭序などの大作、臨書、絵画、自用印まで一堂に紹介。また、千葉県書道協会の会長として千葉の書道界隆盛に尽力した業績を記念して、千葉県書道協会役員展も併催されています。

㊨「九霊太妙」 昭和58年(1984年) ㊥「寒山詩」 昭和37年(1962年) 4幅 = 第14回毎日書道展準大賞

師の思い出を語る(右から)小原天簫、宮負丁香、伊場英白、飛田冲曠の4先生
10月6日には、浅見先生が率いた書星会の宮負丁香理事長、伊場英白副理事長、小原天簫、飛田冲曠の4先生による座談会も開かれ、師との出会いや厳しかった指導ぶり、書風について語りました。
宮負先生は「大学1年の時に先生の所へ連れて行ってもらったが、ちょうどその年に浅見先生が日展で菊華賞(「良寛の詩」1968年)を受賞された。羲之系のすばらしい作品で、いまだに目に焼き付いている。いま生誕100年の展覧会を企画しているが、ぜひ作品を収蔵している千葉県立美術館からお借りして展示したい」と述べました。
小学5年から師事した⼩原先生は、浅見先生が子どもたちにも「千葉県小中高校書き初め展覧会」など5つの書展に出品させ、「大変高いレベルの指導をされていた。賞をいただいた時は、眼鏡の奥の目を細めて笑ってほめて下さった」と振り返りました。
学生の弟子には徹底して臨書をさせたという指導法について、宮負先生は「何十枚も持って行って先生の机に置くと、2~3回見て『ダメだね』とおっしゃる。ある時、王鐸を書いて行ったら怒られ、『学生時代は唐以前のものをしっかりやりなさい』と指導された」。伊場先生は「学生時代に作品を持ってお稽古に行ったら、まじまじと僕の顔を見て『伊場君なあ、たまには酒を飲んで字を書いてみろや』と言われた。もっとおおらかに、気持ちを大きくということだと思うが、いつも頭の中に残っている」。飛田先生は「作品は書き出しの一画で決まるんだよ、と言われた。お稽古で直される時も、だいたい最初の三文字くらい。『打ち込みが弱いんだよ』と。覇気、やる気、気持ちの問題ということを教えられた」と、若き日に師から与えられた忘れがたい言葉を語りました。
浅見先生の書作について、飛田先生は「才能が満ちあふれていて、一本調子ではない。筆の遣い方も逆筆、直筆、側筆と、踊りを踊るような感じだった」と表現しました。宮負先生は「書表現をある時期、ある時期でガラッと変えている。唐以前の書で感覚を作り上げられていると思うが、最終的には若い時に師事した手島右卿先生が根底にあるのではないかと思う」と指摘。「ただ、器用なので王鐸や傅山を見るとパパっと表現できてしまう。ある時、(次々に変わっていく)浅見先生の書を追っていたらダメだと思い、宋の時代の字を書いて持って行くと、『僕は宋代はやっていないんだよ』と言われ、『ぜひやりなさい』と励まされた。それがいま書いている字のきっかけになったと思っている」と述べました。
伊場先生は印象に残っている「この一点」として、浅見先生の絶筆となった尾崎放哉の句「咳をしても一人」を挙げました。鳥取市に建てられる放哉の句碑の字を頼まれていた先生が、入院中のベッドで上向きのままメモ用紙に鉛筆でしたためた時の様子を回想し、「書かれている姿とともに印象深く残っている」と語りました。
座談会で何度も言及されたのは戦争体験。浅見先生は海軍飛行専修予備学生を志願して海軍航空隊に入り、特攻隊として出撃を待つ間に敗戦を迎えました。飛田先生は「戦争体験があるので人間的に強い。自分に対しても厳しかった」。小原先生は「先生の書を理解する上で忘れてはならないものは戦争体験。亡き戦友への鎮魂歌と、平和への祈りが作品の中に込められている」と語りました。
宮負先生は「ある時、寿司屋で飲んでいて遅くなり、『先生そろそろ帰りましょう。あしたがありますから』と言ったら『あしたなんかねえんだ』と怒られて、ああ特攻隊だなと思った。お酒を飲んでいて叱られたのはその一回だけですね」とエピソードを語りました。
座談会の最後は、千葉県立船橋高校で浅見先生から書を教わった6人が観客席から前に呼び出され、「ユーモアあふれる指導で、生徒一人一人にお手本を書いて下さった」などと思い出話を披露しました。

「良寛詩」 平成11年(1999年)

器に揮毫した作品も展示。左奥は「良寛詩六首」 平成24年(2012年) 錦龍卒壽展(個展)出品作
2019年10月8日(火)18:56
銀座・和光で「書業六十五年記念 井茂圭洞展」始まる

井茂圭洞先生の書業65年を記念する個展が10月4日、東京・銀座の和光ホールで始まりました。10月14日まで開かれています(最終日は午後5時まで)。1階のウィンドーには開幕前から留袖に揮毫した作品の写真が飾られ、多くの人が足を止める姿が見られました。
東京での個展開催は今回が初めて。個展の開催そのものも先生が作品60件を神戸市に寄贈された翌年の2016年、「受贈記念展 井茂圭洞の書」が神戸市立博物館で開かれて以来となります。
 井茂先生は当サイトの連載企画「わが古典」のインタビューでも語られている通り、1954年に地元の兵庫県立兵庫高校の書道部で深山龍洞先生に師事されました。
井茂先生は当サイトの連載企画「わが古典」のインタビューでも語られている通り、1954年に地元の兵庫県立兵庫高校の書道部で深山龍洞先生に師事されました。
それから65年を数えるのを記念する今回の個展には、屏風5点をはじめ軸装、額装など45点を出品(旧作2点を含む)。万葉集や良寛、若山牧水などの和歌を題材にしたかな作品が並んでいます。
中には、上智大学の学長を務めたヘルマン・ホイベルス神父の言葉「病者の祈り」を調和体で書いた作品も。夫人がご子息の学校の「母の会」でもらってきた印刷物で目にした文章で、「いつか書こうと思って何十年もしまっておいたもの。新聞の切り抜きでも個人の言葉でも、いつか書きたいと思うものに出くわすと溜めておきます」とのことでした。
-350x268.jpg) 井茂先生は個展カタログに寄せた一文で「書の古典だけでなく様々な分野の芸術と、自然世界が渾然一体となった境地を制作の源泉としておりますが、そこで一番大切なのは、書線が心臓の鼓動の軌跡であり、呼吸の形象化であるということに思い至りました」と述べ、「にもかかわらず、書制作の核となる創造魂を目に見える形に表現することに依然として四苦八苦しております」と書芸術を究めようとする作家の思いを吐露されています。
井茂先生は個展カタログに寄せた一文で「書の古典だけでなく様々な分野の芸術と、自然世界が渾然一体となった境地を制作の源泉としておりますが、そこで一番大切なのは、書線が心臓の鼓動の軌跡であり、呼吸の形象化であるということに思い至りました」と述べ、「にもかかわらず、書制作の核となる創造魂を目に見える形に表現することに依然として四苦八苦しております」と書芸術を究めようとする作家の思いを吐露されています。
2019年10月4日(金) ~14日(月) 10:30~19:00 ※最終日は17:00まで
東京・銀座 和光本館6階 和光ホール
6日(日)、12日(土)いずれも14:00から、井茂先生によるギャラリートークを予定

2019年10月4日(金)12:09
中国展 華やかに祝賀懇親会
9月27日、福山ニューキャッスルホテルで中国展の入賞・入選祝賀懇親会が華やかに行われました。中国展は29日まで、広島県立ふくやま産業交流館「ビッグ・ローズ」で開かれています。

髙木聖雨審査部長のあいさつ

読売新聞社賞の皆さん
2019年9月28日(土)08:24
中国展_開幕
「関西展」に続き、「中国展」が9月27日、広島県立ふくやま産業交流館「ビッグ・ローズ」で開幕しました。29日までの開催です。
JR福山駅北口広場から会場まで、無料のシャトルバスが運行していますので、ぜひご利用ください。



2019年9月27日(金)10:00
遠山記念館で特別展「古筆招来 高野切・寸松庵色紙・石山切」
「公益財団法人 遠山記念館」(埼玉県比企郡川島町)で、平安~鎌倉の古筆を中心とする特別展「古筆招来 高野切・寸松庵色紙・石山切」が10月20日まで開かれています。30年ぶりに展覧会での公開となる個人蔵の2点、「寸松庵色紙」(「山さとは」)と「石山切 伊勢集」(「しるらめや」)を含む書跡24点と、蒔絵調度や小袖など総計30点で構成しています。

「伝紀貫之 高野切 古今和歌集」3点の展示風景
美術館に入って左手の展示室には、まず古今和歌集「高野切」(第一種)巻一の3点を並べて展示。①五島美術館蔵の巻頭(重要文化財、歌番号1~3) ②遠山記念館蔵の2首(歌番号9~10) ③出光美術館蔵の4首(重要文化財、歌番号46~49 ※展示は9月29日まで)──の3点を順番に追うことで、筆運びの変化が見て取れます。 9月13日に行われた報道内覧会で、久保木彰一学芸員は「巻物20巻の高野切は3人の能書家が書き分けているが、スタート部分は一番の書き手が担当した。①は最適な緊張感をもってゆっくりスタートし、②は少し緊張がほぐれたなという辺りで、③では肩の力も抜け、どんどんスムーズに、リズムカルに書き進んでいる。見比べると、書き手の心の中まで覗くように鑑賞していただける」と解説しました。
同じく古今和歌集を書いた「寸松庵色紙」も、「高野切」と同じく3点並べて展示。①遠山記念館蔵の「むめのかを」(歌番号46) ②五島美術館蔵の「あきはきの」(歌番号218) ③個人蔵「山さとは」(歌番号214)──のうち、30年ぶりに展覧会への出品が実現したという③は唐紙の保存状態が良く、墨色がくっきりと鮮やかです。 また、①遠山記念館蔵「寸松庵色紙」に書かれた「むめのかを」の歌は、その右手に展示した出光美術館蔵の「高野切」にも書かれており、異なる能書家が書いた文字を比較することができます。「高野切」は巻子本に行書き、「寸松庵色紙」は粘葉装の冊子本に1ページずつ散らし書きと、それぞれの形式は異なるものの、久保木学芸員は使用した変体仮名や文字の大きさに共通性があり、2人の能書家が仮名に対して近い美意識を有していたことがうかがえると指摘しました。
続いて展示するのは、「本願寺本三十六人家集」の「貫之集下」「伊勢集」の断簡「石山切」4点。藤原定信筆の「貫之集下」2点、伝藤原公任筆の「伊勢集」2点が並び、唐紙などに継紙技法を駆使し、金銀泥による下絵を施した華麗な料紙も見どころとなっています。

「石山切」4点の展示風景
ロビーを挟んでもう一つの展示室(70㎡)には、遠山記念館が所蔵する藤原俊成、藤原定家(「明月記」断簡、「後撰集歌切」)など平安~鎌倉の古筆をはじめ、一休宗純の仮名消息(室町時代)などの書跡、重要文化財「秋野蒔絵手箱」(鎌倉時代)、江戸時代の蒔絵硯箱、文字入模様単衣・小袖などを展示しています。

藤原定家の書跡(いずれも遠山記念館蔵)
右 : 後撰集歌切 鎌倉時代・13世紀
左 : 記録切 明月記 鎌倉時代・建暦3年(1213年)10月
なお、展覧会図録には今回出品された「高野切」「寸松庵色紙」「石山切」の10点を原寸で掲載。それに遠山記念館の所蔵品から出品した古筆のうち6点を収録しています。
◇
2019年9月14日(土)〜10月20日(日) 特別展「古筆招来 高野切・寸松庵色紙・石山切」 公益財団法人 遠山記念館(埼玉県比企郡川島町)
2019年9月24日(火)14:00