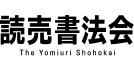お知らせ
東京展ギャラリートーク 角元正燦先生
角元正燦先生 9月2日、国立新美術館
東京展の最終日、角元正燦先生(漢字)が第35回展記念の特別展示「読める書への挑戦」を解説されました。
 角元先生は漢字かな交じりの書である調和体について、「漢字・かなという異質なものを調和させて書くのは難しい」とした上で、「かなのルーツを考えると、もともと王羲之の草書から変体がなを作っている。かなも基の漢字をイメージしながら書くと、漢字に負けない強い字が書けると思います」と、基本を学ぶ重要性を強調されました。
角元先生は漢字かな交じりの書である調和体について、「漢字・かなという異質なものを調和させて書くのは難しい」とした上で、「かなのルーツを考えると、もともと王羲之の草書から変体がなを作っている。かなも基の漢字をイメージしながら書くと、漢字に負けない強い字が書けると思います」と、基本を学ぶ重要性を強調されました。
また、「書は晩成の芸術です。ピカソなどのように、若くして天才が出ることは絶対にない。人生の苦渋や年輪があって初めて表現できるものです。どんなに才能があっても、見る人が見れば『よく手が動いているね』と言うだけです」と述べられました。また、「呉昌碩(中国・清朝末~近代)は『最後の文人』と言われますが、60歳前の作品を見ると若書きです。富岡鉄斎も80歳、90歳になってからの作品がすごい」と例に挙げられました。
角元先生は、西川寧先生の手紙2通を示して「西川先生が青山杉雨先生に与えた手紙は、明らかに後世(この手紙が)残されるであろうと意識して、きちっと書かれている。文章にも無駄がない。しかしとても自然でしょう」と述べ、自分の師である青山先生が調和体について「手紙を書くように書けばいい」とおっしゃっていたことも紹介されました。
自分と同郷の徳島出身である小坂奇石先生の作品は、「デッサン力がすぐれています。書家のデッサン力は、古典をそっくりそのまま書く訓練。皆さんがここまで先生方の作品を見てきても違和感を覚えないのは、書が線の芸術であることを実証した結果なんです」と、長い鍛錬に基づく線の確かさを指摘されました。また、殿村藍田先生の作品「浦島」については「これほど能筆の人はなかなかいない。天才的ですよ。しかも計算して書いたんじゃない。動物的な感覚ですね」と評されました。
自分の師である青山杉雨先生が「現代書道二十人展」に最後に出品した作品は、「ベッドの上に置いた仮設の机で書いたもの。文鎮代わりの石を(病院の近くで)探すのが大変でした」と思い出を語られました。
特別展示に続いて、8月25日に94歳で亡くなられた古谷蒼韻先生の作品を解説されました。角元先生は「古谷先生の臨書は、一つの字を自分の手に入るまで繰り返し書き、自分の感覚になるまで作り直すものでした」と語り、古谷先生自身が「臨書というより、どういう書き方か、探りの勉強です」と述べられていた古典学習法を紹介。また、「普通は親指に力を入れて書くが、先生は小指に力を入れ、ゆっくりと書かれた。体力がないとこんな書き方は出来ない。一つの線に変化がありますが、筆を浮かせて書いたらこのような線は出ません」と指摘し、逝去を惜しまれました。
2018年9月3日(月)17:00