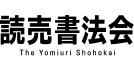お知らせ
東京展ギャラリートーク 大澤城山先生
大澤城山先生 8月30日、国立新美術館
大澤城山先生(漢字)が第35回展記念の特別展示「読める書への挑戦」を解説されました。
読売書法会が取り組む漢字かな交じりの「調和体」について、大澤先生は「まだ熟さない、発展途上の分野」と述べ、「まず漢字とひらがなの特性がまったく違う。漢字は直線的で画数が多く、密度が高い。ひらがなは曲線的で画数が少なく、水と油のようなものです。もう一つ大変なのは可読性と芸術性の両立で、読めさえすれば調和体かと言うとそうではなく、技法や芸術的要素がなければ作品にはならない」と書く立場からその難しさを語られました。
しかし、「教科書も新聞も雑誌も活字。それに今は、文字を『書く』と言うより『打つ』時代で、手書き文字に味わいを感じることも難しい。変体がなや連綿、散らし書きが読めない方々に、書を読んでもらうにはどうすればいいか。調和体では、それらの表現が制約される中でも書作品として芸術性を高める努力と研究が、この先十年、二十年、なされていくと思います」と考えを述べられました。
大澤先生は、先達の作品を一つ一つ紹介。西川寧先生の手紙の前では、「調和体の原点は手紙だとおっしゃる先生がいますが、私もそう思う。手紙は相手に対して書きたいという思いがあるから、心と手が一体になる。だから自然なんです。読めなかったら手紙の意味をなさないので、そんなに装飾的になる必要もない」と説明されました。
しかし、それは決して簡単なことではなく、「よく『書を習いたい。展覧会に出すような大きな作品は書かなくていい。ちょっと手紙が書ければいいから』とおっしゃる方がいますが、それが一番難しい。自然に書くというのは、相当な力量がないと出来ません」と付け加えられました。
自分と同郷(長野県松本市)の上條信山先生の作品の前では、「上條先生の書を見ると、いつも北アルプスの急峻な山、槍ヶ岳や奥穂高岳を思い出します」と語り、高校の校歌を書いた「伊那弥生ヶ丘高等学校旧校歌碑」については「かなり可読性を意識して書かれたと思われますが、信山先生の特徴がよく表れています」。先達たちの作品が、たとえ平明に書こうと意図したものでも品格を失わず、おのずと個性が表れていることを指摘されました。
最後に大澤先生は「やはりこの時代に生を受けた以上、時代の影響を当然受けるわけですし、この時代に生きた書家だからこそと言える書を残さなければおかしい。調和体はまだ未完成な分野だからこそ、可能性は大きいと思います」と語り、「私も今回、調和体の作品を書きました。自分の言葉を常々書きたいと思っており、長野県出身なので長野県にまつわる作品を書きました」と結ばれました。
大澤先生が調和体作品として書かれた言葉は次の通りです。
「八ヶ岳の麓 そこには黒曜石の恵みを活かした 縄文人の叡智の跡」
2018年8月31日(金)19:00