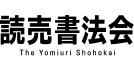お知らせ
東京展ギャラリートーク 牛窪梧十先生
牛窪梧十先生 8月26日、国立新美術館
牛窪梧十先生(漢字)が国立新美術館で第35回展記念の特別展示「読める書への挑戦」の作品を解説されました。
牛窪先生は前置きとして、読売書法会が1995年の第12回展から「調和体」部門を新設し、漢字かな交じりによる「読める書」に取り組む以前から、書道界では時代の変化に応じた書が長く模索されてきたことを説明されました。
また、「普通われわれが目にしているものは、漢字とかなが違和感なく並んでいるように見えますが、書として造形的に表現する立場から言うと、なかなか簡単には行きません。漢字は直線性が強くて構造的、かなは抽象化されたもので曲線を主としている。漢字は一文字でも意味を持つ表意文字、かなは表音文字という違いもある」と、基本的性格の違いによる書作の難しさを語られました。
特別展示には、読売書法会の伝統につながる先達が、調和体部門の発足以前に書かれた作品も多く並んでいます。牛窪先生は一つずつ紹介しながら、「調和体とは何か」を考える上で示唆となる要素を挙げられました。
たとえば上條信山先生の作品は、西郷隆盛の詩が漢字とカタカナによる読み下し文として書かれています。牛窪先生は「漢字と、同じく直線性のあるカタカナがマッチしている。こういう書き方もあります」と解説されました。
ほかにも墨の潤渇の変化、大胆な言葉の配置などの構造的な工夫や、自詠の詩や現代短歌といった題材の選び方も、参考になる作例として挙げられました。
会場には、牛窪先生の師である西川寧先生の手紙も2通展示されています。その1通は、青山杉雨先生から金魚を贈られたことへの礼状。「美事なる金魚難有存上候」という書き出しで、ユーモアのある内容です。
しかし、牛窪先生によると西川先生は手紙を大の苦手とされていました。「西川先生は造形性の感覚が強い方。手紙のように一発勝負で書くものは、必ず途中で気に入らない所が出てきてしまう。だから何となく手紙を避けておられたと思われるフシがあります」とのことです。
しかし青山先生宛ての手紙は、文章の歯切れもよく、書きぶりも大胆です。牛窪先生は「勝手に推測するに、作品として意識して書かれたのではないか。王羲之など昔の書家たちも、手紙(尺牘)の字がとても大きく、お互いに書として見せ合う意識で書かれたものではないかと思います。西川先生の手紙にも、たぶんその意識があったのではないか」と述べられました。
また牛窪先生は、特別展示の作品の中には西川先生が小説家の正宗白鳥の字を評した文章を意識したものがあるのではないか、と推測されました。西川先生は1957年、雑誌「書品」に発表された文章で、白鳥が書いた色紙を「この人のいのちが筆に密着して、端的直截に出ていて」「一所懸命に、言いかえれば何の意もつけずにかいている」と絶賛しています。
牛窪梧十先生は「西川先生は淡々として書けばそれが一つの作品になり得るんだと主張された。書道界の先生方はその文章を読んでいたはずです」とその影響力を推測。たとえば小坂奇石先生の「佐藤春夫の詩」(1966年)には「それこそ白鳥の字をほうふつとさせるような要素」があり、青山杉雨先生の「田中冬二詩」(1961年)も「心の動きを素直に追っていく作品のつくり方で、西川先生の主張を受けた一つの姿であろうと思います」と述べられました。
多くの先達が、自分たちの生きる時代にふさわしい書のあり方を模索し続けてきたこと、その作品が今後の調和体を考える上でも大きな示唆になることが、改めて感じられたトークでした。
2018年8月30日(木)16:40