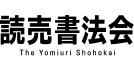お知らせ
東京展ギャラリートーク⑧ 大澤城山先生
■大澤城山先生(漢字) 8月29日、東京都美術館
執行役員以上の先生方の調和体作品を中心に解説されました。
 大澤先生は「それぞれの先生が専門とする漢字やかなとは違う調和体作品をどのように書いておられるか。同じ漢字作家でも、得意とする書体による違いも見どころです」と指摘しました。
大澤先生は「それぞれの先生が専門とする漢字やかなとは違う調和体作品をどのように書いておられるか。同じ漢字作家でも、得意とする書体による違いも見どころです」と指摘しました。
また、調和体と漢字を半々くらいで出品している自身の立場から(昨年は調和体、今年は漢字の作品を出品)、「調和体の楽しみ方の一つは、作家がどのような言葉を選び、その言葉を通して何を表現したいのかだと思う。私は調和体の方が言葉を選ぶのにエネルギーを使います。共感し、感動して、自分の思いを託せるような言葉を見つけるのに苦労する。自分で言葉を作るにしても、何をアピールしたいのか、メッセージ性は何なのかを考えます」と述べました。
井茂圭洞先生(かな)の作品は、文部省唱歌「朧月夜」の一番「菜の花畠に 入日薄れ」。大澤先生は「日本の原風景を感じさせる歌。渇筆や潤筆を効果的に配し、技術的にも視覚的にも見ごたえがある。この全体感ですね。私の住む松本(長野県)からは北アルプスの山並みが望まれ、麓には安曇野の田園風景が広がるが、私の持つイメージと一致します。抒情的な作品ですばらしい」と述べました。
また、自分も2009年、日本の在外公館に書作品を贈る全国書美術振興会の事業で、同じ長野県出身の髙野辰之が作詞したこの歌詞を選んだことがあり、「アフリカの在タンザニア日本大使館に飾らせていただいています。まだ見たことはありませんけど」とユーモアを交えて語りました。
95歳の尾崎邑鵬先生(漢字)は、大野修作『書画綴英』の一節「王鐸と傅山」を縦の4行書きにした作品。「縦の作品を書かれるのは体力的にも大変ではないかと思うが、一文字目から最後まで気脈から何から貫通させて書くのは、体力はもちろん、気力が充実していないと書けない。細いけどピアノ線のようにキリっとした強い線なので、黒の面積はそれほど多くないが、決して白には負けていない。そして行間を空け、明るい作品に仕上げておられる」と評しました。
梅原清山先生(漢字)も97歳にして気力のみなぎる作品。「強靭な線で大きめの楷書を多く発表されるが、調和体も大字の楷書で鍛えた、石に刃物で刻んだようなキリっとした線で書いておられる」と述べました。
大澤先生は「漢字、かなの混合度合いが悪くないのが第一」という梅原先生の自作コメントを引用した上で、「(書く言葉を選んで)これでいいと思っても、今度は漢字とひらがなのバランスの問題が出てくる。画数が多くて密度の濃い部分が出せる字と、少ない文字のバランスが難しい。縦に書いてみたり横に書いてみたりするが、歌ならサビに当たる所にいい文字が来てくれればいいけれど、そうとも限りません」と制作の苦心を述べました。
星弘道先生(漢字)の「ジョン・ラボックの語」は、「漢字の先生らしく、紙面全体を揃え、行をしっかり立てて行間を空けるという表現。『藝』という画数の多い文字を(中央に)配置したことで、大きな盛り上がりを作り、左右の余白に響かせている」。また、「字数が少ないので、これだけの紙面を埋めるには線質が強くなければならない」と指摘し、細身になりがちなひらがなの「よ」「さ」の横棒を長くして、幅を広げて見せようとした意識が感じられる点などの工夫を挙げました。
2019年9月11日(水)11:10