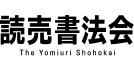4.書法会役員の書活動
対談 「明末清初の書」開かれる
対談「明末清初の書」
高木聖雨・読売書法会常任総務 + 富田淳・東京国立博物館学芸企画部長
11月25日 午前11時~12時30分 東京・静嘉堂文庫美術館講堂
東京・世田谷区の静嘉堂文庫美術館で開催されている「あこがれの明清絵画展~日本が愛した中国絵画の名品たち~」(12月17日まで)は、江戸時代以来、日本人が集めた明清時代の書画を、日本の文人たちの跋や模写と共に展観する試みで、同美術館のコレクションの豊かさを実感させる企画です。六本木の泉屋博古館の「典雅と奇想 明末清初の中国名画」(12月10日まで)と合わせ、明清の書画を鑑賞する絶好の機会となっています。
11月25日、静嘉堂文庫美術館で両館の連携企画として、読売書法会常任総務の高木聖雨先生と東京国立博物館の富田淳学芸企画部長の対談「明末清初の書-連綿趣味の魅力を語る-」が開かれました。約1時間半にわたり、歴史的背景の解説から書作の現場に迫る分析まで、白熱した議論が展開されました。
明末清初は、16世紀半ばから17世紀半ばにかけて、漢民族の明王朝が揺らぎ、満州族の清が建国された混乱、動乱の時期でした。権威の動揺と王朝の交代は、創作においては自由な個性的表現を生みます。政治的な混乱の一方、富裕層は新しい書を求め、高い壁をもつ居空間に適した長条福が発達。時代精神とあいまって、連綿草がダイナミックな展開を見せました。
文人たちの生き方はさまざまですが、時にその処世術が儒教的な道徳に反する結果を生み、後世の中国の人々の誹りを受けることもありました。宦官に追従したとされる明末の張瑞図は、権力者の失脚とともに作品もろとも否定され、明清の二王朝に仕えた王鐸は「忠臣は二主に事えず」という儒教観に反する「弐臣(じしん)」の典型例として歴史上に汚名を残します。
一方、明に殉じた倪元璐は英雄的な扱いです。遺臣としての考えを貫いた傅山も義臣として高く評価されました。
清初という時代は、漢民族に対して満州族の辮髪を強制する「薙発令(ちはつれい)」が発せられ、「頭を留めるものは髪を留めず 髪を留めるものは頭を留めず」という言葉に象徴されるように、厳しい二者択一が迫られた時代でした。
もっとも王鐸が「弐臣」として否定されるのは後の乾隆帝の時代のことで、存命中は政府高官として厚遇されています。
いずれにせよ、張瑞図、王鐸は中国で軽視された結果、江戸時代以来、優れた作品が日本にもたらされ、その中の優品が今、静嘉堂文庫美術館で展示されている、ということが出来ます。
対談では、そうした時代背景とともに、明末清初の六大家を中心に、人物像を示すエピソードをふくめ、さまざまな話が繰り広げられました。
作家別にお二人の話を追ってみましょう。
米万鐘
富田(TO)書風の印象は?
高木(TA)
白を基調した作品で それがまず目に入ります。
王鐸や傅山の強い作品と比べると、明るい作品の先駆者だと思います。
長条幅の時代なので、どうしても文字が縦に縦に長くなります。連綿を縦に伸ばすために 連綿の線を下に長く取っています。ほとんど文字が長方形に立ってきていると思います。四角に囲まれた文字が少なくなってきますね。
条幅は南宋の後に出てきます。それ以前はほとんどが巻子です。そして明の時代に長条幅が盛んに書かれるようになり、連綿草も発達します。建築様式の変化、動乱の時代という背景がありました。考えてみれば、顔真卿も盛りを過ぎた唐が混乱期に向かう時代の節目に登場しました。不安定な時代には新しいものが生まれやすいのかもしれません。
張瑞図
人物について:
TO
万暦35年(1607年)、38歳の時に 3番の成績で進士になったエリートです。天啓年間(1621~27)に権勢をふるった宦官・魏忠賢のもとで出世を遂げますが、魏忠賢失脚直後に郷里に隠棲。
行草書に優れ、画は元末の黄公望を学んで山水をよく描きました。
いわば悪代官に尻尾を振って出世した軽薄な人物、として後世に悪名を残しましたが、見方によっては違う一面も見えてきます。
魏忠賢が皇帝から祠の建設を許可されたときのことです。扁額を誰が揮毫するかが話題になりました。 当時、書画の実力者といえば董其昌か張瑞図です。
魏忠賢は権勢をほしいままにして政治を乱した権力者です。その魏忠賢のために揮毫するということは、後々災厄を招く可能性がありました。
董其昌はその危険を察し、「馬から落ちて腕を痛めた」という噂を自ら捏造、流布し、首尾よく指名から逃れました。董其昌は優れた官僚、文人でしたが「悪者」
の一面もありました。それだけにこうした危険を察知する勘もよかったようです。
董其昌が駄目となれば張瑞図、ということになります。張瑞図は董其昌のように予防線を張る賢さ、狡さはなく、いわば無防備のまま、揮毫者に指名されてしまいました。
指名されてこれはどうしたものか、と悩みます。
書かなければ魏忠賢に殺されてしまいます。書いたら将来どのようなことになるかわかりません。
結局、魏忠賢のために扁額を書きますが、書いた後「このままではいられない」という思いにかられたようです。
ほどなく皇帝が交代し、魏忠賢は死に追いやられ、一族郎党も罪に問われました。
張瑞図は辞職を望み、故郷・晋江に帰ります。しかし、魏忠賢一味の罪状調査の中で扁額の件が発覚し、それまで張瑞図を庇っていた皇帝・毅宗もこれには怒りました。張瑞図逮捕のために役人が晋江に差し向けられます。
絶体絶命の危機です。
ここで張瑞図は一世一代の芝居を打ちました。
狂人のふりをしたのです。顔やからだに汚物を塗りつけ、「あはは」と笑って、わらの上で犬の糞を食べるのです。
捕らえに来た役人も「あ、これは狂ってしまった」と思い込み、朝廷に奏上。張瑞図は平民におろされはしたものの、それ以上の処罰は受けずにすみました。
この話にはオチがあります。張瑞図が食べた「犬の糞」は実は高級食材を使ったお菓子だった、というのです。「糞」を食べた後の至福の笑顔は演技ではなく、それだけに役人も騙されたのでしょう。
書について:
TO (スクリーン上の張瑞図の作品では)弧を描くような旋回が張り出してきて
います。
TA 大学で張瑞図を書く人には、「木の葉落としだ」と説明します。ひらひら落ちてくる感覚です。
明らかに木の葉が落ちてくるリズム感があります。
そして米万鐘と比べると一行の字数が詰まってきます。つまり連綿が違うのです。
次の文字に続ける時 、最短距離で次の文字へ移りますが、米万鐘や王鐸は もっと下まで来ています。
張瑞図はここで、明末=ロマンチシズムの時代を背景に独自の世界を築きます。
人とは違う、自分らしい作品を書こうとしたように見えます。
富田先生、学生からよく聞かれるのですが、誰に倣ったらこうなるのでしょう。
TO 個性的な人が多い時代で、張瑞図が何を習ったのか、何をベースにしているかよく議論されるところです。 結果としてこうなっています。 若い頃は王羲之です。
王義之を学び、そこから自身の書風へと進んだ際のエピソードが伝えられています。
書をたしなむ人は自分の指を筆に見立てて いつでもどこでも練習を繰り返すものですが、張瑞図も同様でした。
ある晩、いつものように昼間勉強した王義之の書を指でなぞるように復習していたところ、気がついたら隣で寝ていた妻のお腹の上に指で字を書いていました。
妻は思わず「あなた何やっているの? 」と聞きます。
張瑞図が「王義之の書を」と答えたところ、妻に「なぜ人の文字を真似するの?」と問い返されました。
それが転機となって自分の世界を切り拓いた、という話です。
TA さっそく学生に伝えましょう。
TO
「木の葉落とし」とは違う特徴を持った作品もあります。たとえば草書を混ぜて書いた「草書五言律詩」は、文字の大小をつけずに書いた、かなり平易な作品です。
(スクリーン上の)王維の詩を草書で書いた巻物の作品は、終わりの部分などは大変な力量で迫ってきます。書くのが楽しくてしょうがない、という感じが伝わる作品ですね。
こうした草書的な作品が晩年作なのか、「木の葉落とし」が晩年なのか、制作年代を定めがたいのですが、張瑞図には董其昌に近い明るい作品と、力強い線質の時代があることがわかります。
張瑞図の作品については、「くすんで茶色くなった作品ほど本物」という説があります。号が「二水」だったので、火事除けとして土間に飾られて煤を吸ったからだ、と言われます。
TA
巻子は手元で見るので、常時開いているわけではありません。そのために真っ白な状態が保たれることもあるのに対し、条幅は壁で晒され、焼けやすいという面があります。巻子は書かれた当時のままのものもありますが、よく見られた作品は黄色く変色しており、これなどは「見られた歴史」を物語っているといえそうです。
TO
巻子は展覧会では5メートルもある長いケースで展示することもありますが、基本的に自分の腕の幅で巻いて見るものです。一度に見られるのは腕の幅ということになります。巻きながら、巻頭から巻末に進む展開は、映画を見るような体験でもあります。
絹本について
TO
絹と紙は、書いていてどれほど感触が違うものでしょうか。
TA
絹本はかすれが出やすいですね。下手をするとかすればかり。
(値段は)高いですけれども、絹本の方が書きやすいですね。
(スクリーン上の作品は)文字の大小をつけていない。ことさらに見せようという、意図的な制作がなく、本当に一気呵成に書いたのが伝わってきます。
われわれが書く時は、どこかに大きな文字を入れたり、小さな字を入れたりして立体感を出そうとするのですが、これは線の多彩さはあり、立体感はあり、手腕が確かですね。
TO
絹本は焼けが早く、茶色くなりやすいのですが、最初はもっと白に近い状態です。
以前、京都の文化財の保存・修復を行っている会社で裏彩色をした絹本を見せてもらったことがあるのですが、少し離れると、表か裏か当てられなくなりました。
それくらい透明だったということです。
王鐸
人物について
TO
天啓2年(1622年)、31歳(30歳?)で 進士に合格しています。同期に倪元璐、黄道周がおり、共に出世したのですが、王鐸は順治2年(1645年)、清に降伏し、翌年、清朝に迎えられました。倪元璐、黄道周は明に殉じたのとは対照的で、清王朝でも優遇され出世を遂げた王鐸は、後に「弐臣(じしん)」と呼ばれ、白眼視されることになります。
そのため王鐸は最近まで評価されませんでした。これがある意味で日本には幸いし、日本に名作が流入することになりました。
村上三島先生も王鐸の良さを認め、作品を多く買い求めました。ある時、村上先生が中国の人に「王鐸はいい作品が多いから、展覧会しないか?」と問いかけたことがありました。それに対する反応は、最初は「やってもいいけど」という程度のものだったそうです。ところが村上先生の持っている何十本、何百本の王鐸の作品を見て考えが変わり、中国側もこれはすごい、と収集を始めたといいます。
「弐臣」の問題は中国ではそこまで影響力が大きい、ということも出来るでしょう。
TA
私個人としても好きなのは王鐸ですね。弐臣の最たるものですが、それは、いい方向に考えてあげれば、書が好きで、書を書きたいがために清朝に使えて書の人生を全うしようとした、とも考えられます。書を楽しみ、書を書きたいがためにそういう手法をとったのではないか、と。身贔屓かもしれませんが そう思っています。
展覧会では王鐸と倪元璐、黄道周は並べて展示しない、と聞きましたがどうでしょうか。
TO
学芸員は展覧会のたびにどのように見せるかを考えます。ご指摘のようなことを考えることもあるでしょう。
書作について
TA
大学で30〜40人のゼミを持っているのですが、その4割程度が王鐸に倣って卒業制作をしています。
いかに王鐸が若い人に人気があるのかを示していると思います。
王鐸の条幅作品は高さが3メートルに達するものもあり、 文字が縦に長くなる、つまり文字が長方形になりがちです。正方形ももちろん必要ですが、数は減ります。
その上で、独自の線の多彩さ、行の歪みを含みながら、全体が絶妙なまとまりを見せています。
王鐸は書を書くときに机に正対していなかったと思います。 張瑞図は正対していますね。王鐸は机の上で斜めに構え、それで歪みが生じたのだと思います。
墨を多量に使っているのも特徴でしょう。懸書で中央に向かって墨が流れる。そうした情景が目に浮かびます。
王鐸の場合、本文重視で落款は空いたところに入れています。
徹底的に王羲之、王献之、顔真卿を習ったことが伝わってきますね。金石的なものも感じます。
4〜5字の連綿を書くのは王鐸、張瑞図、黄道周くらいではないでしょうか。倪元璐を含め、多くの書家は一文字一文字は連綿しますが、彼らのように続けている人は少ないと思います。
TO
中国の建物は天井が高く、そこで何か掛けようと思うと3メートル超える作品も求められます。これが連綿趣味とリンクする部分も確かにありそうですが、連綿草の展開には内面的な要因もあると思います。
動乱の時代です。国の支配層・士大夫たちは国がどんどん乱れるのを見て「国が潰れるのではないか」、「何とか立て直したい」という思いを抱きます。しかし私利私欲に走る権力者もいて思うようにはいきません。
このやるかたなき鬱憤を背景に、書画にも優れていた士大夫たちは行草書を連綿で書くことによって意味内容以上の気持ちを表現していたように思われます。
そうした連綿の書は、同じ危機意識を持った人の目には「この人もいろいろ考えて悩んでいるのだ」と感銘深く映ったはずです。そして、文人のサークルで珍重されるようになっていきます。
TA
王鐸の魅力はさまざまですが、青山杉雨先生は「王鐸はうまい。傅山はいい字」と評していました。
王鐸は本当にうまい。王義之、王献之、米フツを徹底的に学んでおり、それがしっかり表れています。
作品を王鐸はそれを自家薬籠中のものとした上で、個性を発揮し、古典の匂いがする独自の作品を生み出しました。
「呉昌碩の行草の臨書すると王鐸を臨書した気持ちになる」という学生がいました。徹底的に学んだものが深いところ浮かび上がってくるのかもしれません。呉昌碩と王羲之の間に、ヘソのような存在として王鐸がいるのではないか、と思います。
360度の動き、空間の大きさ、一気呵成に書き上げる自由さも王鐸の魅力的で、それで王鐸が好きなのかもしれませんが、一歩離れて考えると、王鐸の作品を見る機会が多いことも背景にありそうです。
董其昌
TO
六人の中では最初に活躍した明末の文人で、生まれたのは嘉靖34年(1555年)、没したのは崇禎9年(1636年)です。
万暦17年(1589年)、35歳で進士となり高級官僚の道を歩みますが、病気などを理由に何度も職を辞して郷里の江南へ帰っています。何かあると北京で仕官し、また理由を見つけて故郷へという繰り返しでしたが、辞職・帰郷は粛清を回避する高等技術でもあったようです。
(スクリーン上の)49歳の時の巻物を見ると、謹厳に書き始め、感情が高ぶってきて力が漲り、筆が伸びやかになっています。細字の後、ひと呼吸おいてのびのびと大粒の文字が伸びやかに書かれるなど、あたかも交響曲の趣です。大きな伸びやかな部分を書きたくて前を小さくしたのではないかと思われます。
TA
後半の伸びやかな部分は懐素ですね。そして、自然にひと文字ひと文字、縦長が多くなっています。
北宋 黄庭堅は横に広げた形で連綿を展開しましたが、董其昌は条幅を多く書いていたために、巻子でも条幅の形式が混入してきたと言えそうです。
白を基調にした非常に明るくて強くて真似のできない作品で、筆の捌きのさわやかさなど、書の素晴らしさをすべて包含していると思います。
TO
懐素「自叙帖」を晩年に臨書したものなどは、筆が渋いですね。
「久しぶりに懐素の『自叙帖』を見て臨書をしました」と書いてあります。
上っ面ではないものがあります。躍動感あふれながらも筆が落ち着いています。うまいと思います。
明代中期に活躍した文徴明(成化6年―嘉靖38年:1470年―1559年)は1日に千字文を何度も何度も書くような努力家で、小宇宙を愛し、ここまでのものはないと思わせるほどの作品を残しました。後続世代に影響力を及ぼしますが、形骸化し、硬くなってしまいます。董其昌はそれに反発したと言えるでしょう。
董其昌の瀟洒な書風は、今日取り上げる他の5人にも受け継がれていきます。
黄道周
TO
天啓2年(1622年)、38歳の時に王鐸、倪元璐と共に進士となりました。福建出身で、島の洞穴で受験勉強をしたといい、それが「石斎」という号?の語源になったとされます。
知人の減刑を願い出たり、時局の批判をしたりしたため、降格、免職を被った硬骨の文人でした。牢屋で 書いた書画を監視人に与え、それが功を奏して鞭打ちの刑の際に手加減してもらった、という話も伝わります。監視人に譲られた作品が何十本も残っています。
TA
作品を見ると、かなり気性の激しい人ではなかったかな、と思います。横線が右上がりです。
同じ線を引いても右上がりが強く、そのために懐が狭くなった字があるのですが、どこかで緩めてバランスとっています。右上がりを強くすると狭くなる中で、懐の深さを強調する美学を感じます。
落款の手慣れたうまさにも感心させられています。
TO
「松石図鑑」という大作では、署名が少し緊張して書かれたように見えます。少し動きが違います。大作 の最後で慎重になったような、人間らしさを感じます。
倪元璐
TA
天啓2年(1622年)に進士になった三羽がらすの一人です。30歳の若さでした。
墨をあまり重たく使わず、渇筆が多い特徴があります。
2画目、3画目からかすれてきます。
また、連綿と見せながら、実際は単体で書いているのが多いですね。一文字の中の連
綿にとどまり、字群としての連綿はあまりありません。
晩年はより退廃的になりますので、倪元璐に惹かれている学生には「あまり追い過ぎると行き場を失う」と注意喚起しています。
傅山
TO
故郷の山西省太原で官吏登用試験に及第しましたが、明滅亡後は医術で生計をたて、清へは仕官しませんでした。(生没年は1607-1684年)
連綿を多用し、連綿趣味はこの人のためにあると思われるほどです。
TA
青山先生が傅山の作品を「感興に任せて思うままに書いているから、文字の乱れもある、それでいながら全体がまとまって見える。これが書家の目指す方向だ」と評したことがありました。
確かに「うまい」というよりも「いい字」だと思います。
また、当時としては珍しく篆刻、隷書を手がけた先駆者でもあります。太原には篆隷で書かれた石碑がかなりの数、残っています。
子の傅眉が傅山の書風を継承し、傅山の在世中から代筆もしていました。
これで「傅山」と書かれたらそう思ってしまうような作品が多数残っています。
六大家の周辺
TA
明末清初の六大家、中でも董其昌は華亭派の頭領として永きに亘り影響力をもち一大派閥を形成しました。王鐸、傅山も人気を集め、系譜を見てみると豊富な人材を見る事ができます。そこで他に系譜を見出したいと思い、名も知らない作家を含めた明末清初の作家に興味を抱きました。出来る限りの収集を試みましたが、やはり結論は六大家の影響大という事になります。
しかし名も知らない能書家を見出すことは今に生きる我々の責務ではないだろうか、という気もしています。
*高木先生は、書の研究を深められる中で、明末清初の六大家の周辺や後続世代にも着目し、無名の書家を含めて広く作品を集めておられるそうです。再来年には展覧会を開くご予定とのことでした(編者注)
今回言及された書家は下記の書家でした。
董其昌の系譜
姜逢元、眭嵩年、沈荃、沈白、范塘
毛奇齢
王鐸の系譜
王無咎、戴明説、紀之竹、徐日升、張伯琮
傅山の系譜
傅眉、賀深、許友、何采
黄国琦、蒋衡、謝道承
以 上
2017年12月6日(水)18:00