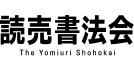2018年8月
東京展ギャラリートーク 日賀野琢先生
日賀野琢先生 8月29日、東京都美術館
日賀野琢先生(漢字)が読売大賞・準大賞、読売新聞社賞の漢字作品を中心に解説されました。
日賀野先生は、読売大賞に選ばれた森上洋光さんの小篆による作品について、「秦の始皇帝が定めた小篆のスタイルだけでなく、清朝時代に復古運動が起きた時に趙之謙、呉譲之、徐三庚といった書家たちが独自にアレンジして書き残した小篆あたりにもヒントを得て書かれている」と指摘されました。
さらに、「小篆の様式美にしっかりはまり、重厚な雰囲気が伝わってきます。ただ、それだけでは作者の鼓動やリズムが伝わらないので、運筆の中に太い・細いの変化をつけています。さらに字の重心を半分より上にして足長(長脚篆)にし、ワイングラスのように高貴でスタイリッシュな姿を演出した。そうすると下部が不安定になるので、終筆の所をちょっと太くして、全体の安定を取っている。線と線の間に空白を作って風通しを良くし、疎なる所と密なる所をうまくミックスさせています」と作者の工夫を細かく分析されました。
読売準大賞の小出聖州さんの作品は、「篆書が隷書に変わっていくあたりを題材にされて書かれている」と紹介。「(篆書が完成された)小篆は作品にしづらいが、ちょっと崩れて隷書になっていくあたりを作品にすると、実は楽しいんです。ものが完成される前や、ちょっと崩れていく過程をうまく題材に採ると、結構自由に表現できます」と述べられました。
同じく読売準大賞の窪山墨翠さんの作品は、一字目に注目=写真=。「筆をボーンと打ち付けたところに、まるで交響楽でシンバルが鳴ってジャジャジャジャーン、と始まるような音楽性を感じます。最初がうまく行って、よしっ、と興に乗られたのかなと思います」と評されました。
同じく読売準大賞の筈井淳さんの作品については、線の粘りを特色に挙げられました。
日賀野先生は「書は追体験ができます。作者が筆を下ろした時の様子を想像し、自分も書いているような気分になる。そのつもりになると、作者のリズム、鼓動が伝わってくる。古典は手習いすることが重要ですが、もう一つ『目習い』といって、目で習うことも大切。皆さんも作品を見る時は、ぜひ追体験して字の流れを追い、それからちょっと離れて全体のリズム感や構成を見ていただくといいかなと思います」とアドバイスされました。
また、書を見に来てくれる一般の人に向けて、「『読めない、分からない、だから書はつまらない』とみんなバリアを張ってしまいます。漢詩を書いた時は、「いい意味の詩だったね」と言われます。私の立場としては、意味を積極的に伝えようとしているわけではなくて、あくまでも文字の姿、形を見てほしいというところがあります」と語りかけられました。
2018年8月30日(木)17:30
東京展ギャラリートーク 吉澤大淳先生
吉澤大淳先生 8月27日、東京都美術館
吉澤大淳先生(漢字)が読売大賞・準大賞、読売新聞社賞の作品について解説されました。
吉澤先生は、読売大賞に輝いた森上洋光さんの漢字作品について「中国・唐代の詩の一節から選んだ26文字を篆書で表現されている。荘厳な儀式が終わって夜明けの光が降り注ぐという内容のようです。ご本人のお話では4月から何度も書き直し、重厚さと美しさに加え、華やかな表現を心がけられたようです」と紹介。「小篆を綿密に重ね、重厚で荘厳な感じのする様式美に仕立てられています。墨量も非常にうまくのっている。すごい腕だなと思うのは、墨が多いと空白が潰れてしまうものですが、非常にうまく残している。しかも細部まで神経が行き届きながら、全体感を失わない。なかなかできない技術であり、作品であると思います」と評されました。
読売準大賞の小出聖州さんの漢字作品は「近年出土の漢代の隷書の肉筆を基にしている。隷書の一番の基本は垂直・扁平・左右相称、字が正面を向くことですが、それをやや右肩上がりに工夫されているのが特徴。その中で安定感とバランスが非常にうまく取られています」と指摘されました。
また、同じく準大賞に選ばれた井谷五雲さんの篆刻作品について「大胆な構成で、造形、白の空間の取り方、字の粗密などの変化が非常にすばらしい。篆刻の皆さんは筆の代わりに字を刻するのですが、線質をじっくり見ていただくと、力強かったり複雑だったり、微妙な変化が見て取れます」と見どころを説明されました。
吉澤先生はかな作品、調和体作品も解説し、「人の作品をよく見ることも、自分の書作を高める上で大きい。漢文、和文、小説、随筆、語録、紀行文、詩歌、童謡、民謡など、この人はこういう題材を書いているんだと思って見るのも楽しい。また、どのような筆・墨・紙や印を使っているかなど、いろいろな角度から自分の意を留めれば、そこに魅力が感じられます」と語られました。
2018年8月30日(木)16:40
東京展ギャラリートーク 牛窪梧十先生
牛窪梧十先生 8月26日、国立新美術館
牛窪梧十先生(漢字)が国立新美術館で第35回展記念の特別展示「読める書への挑戦」の作品を解説されました。
牛窪先生は前置きとして、読売書法会が1995年の第12回展から「調和体」部門を新設し、漢字かな交じりによる「読める書」に取り組む以前から、書道界では時代の変化に応じた書が長く模索されてきたことを説明されました。
また、「普通われわれが目にしているものは、漢字とかなが違和感なく並んでいるように見えますが、書として造形的に表現する立場から言うと、なかなか簡単には行きません。漢字は直線性が強くて構造的、かなは抽象化されたもので曲線を主としている。漢字は一文字でも意味を持つ表意文字、かなは表音文字という違いもある」と、基本的性格の違いによる書作の難しさを語られました。
特別展示には、読売書法会の伝統につながる先達が、調和体部門の発足以前に書かれた作品も多く並んでいます。牛窪先生は一つずつ紹介しながら、「調和体とは何か」を考える上で示唆となる要素を挙げられました。
たとえば上條信山先生の作品は、西郷隆盛の詩が漢字とカタカナによる読み下し文として書かれています。牛窪先生は「漢字と、同じく直線性のあるカタカナがマッチしている。こういう書き方もあります」と解説されました。
ほかにも墨の潤渇の変化、大胆な言葉の配置などの構造的な工夫や、自詠の詩や現代短歌といった題材の選び方も、参考になる作例として挙げられました。
会場には、牛窪先生の師である西川寧先生の手紙も2通展示されています。その1通は、青山杉雨先生から金魚を贈られたことへの礼状。「美事なる金魚難有存上候」という書き出しで、ユーモアのある内容です。
しかし、牛窪先生によると西川先生は手紙を大の苦手とされていました。「西川先生は造形性の感覚が強い方。手紙のように一発勝負で書くものは、必ず途中で気に入らない所が出てきてしまう。だから何となく手紙を避けておられたと思われるフシがあります」とのことです。
しかし青山先生宛ての手紙は、文章の歯切れもよく、書きぶりも大胆です。牛窪先生は「勝手に推測するに、作品として意識して書かれたのではないか。王羲之など昔の書家たちも、手紙(尺牘)の字がとても大きく、お互いに書として見せ合う意識で書かれたものではないかと思います。西川先生の手紙にも、たぶんその意識があったのではないか」と述べられました。
また牛窪先生は、特別展示の作品の中には西川先生が小説家の正宗白鳥の字を評した文章を意識したものがあるのではないか、と推測されました。西川先生は1957年、雑誌「書品」に発表された文章で、白鳥が書いた色紙を「この人のいのちが筆に密着して、端的直截に出ていて」「一所懸命に、言いかえれば何の意もつけずにかいている」と絶賛しています。
牛窪梧十先生は「西川先生は淡々として書けばそれが一つの作品になり得るんだと主張された。書道界の先生方はその文章を読んでいたはずです」とその影響力を推測。たとえば小坂奇石先生の「佐藤春夫の詩」(1966年)には「それこそ白鳥の字をほうふつとさせるような要素」があり、青山杉雨先生の「田中冬二詩」(1961年)も「心の動きを素直に追っていく作品のつくり方で、西川先生の主張を受けた一つの姿であろうと思います」と述べられました。
多くの先達が、自分たちの生きる時代にふさわしい書のあり方を模索し続けてきたこと、その作品が今後の調和体を考える上でも大きな示唆になることが、改めて感じられたトークでした。
2018年8月30日(木)16:40
東京展ギャラリートーク 和中簡堂先生
和中簡堂先生 8月26日、東京都美術館
和中簡堂先生(篆刻)が、篆書の作品を中心に、読売大賞・準大賞、読売新聞社賞、読売俊英賞の作品について解説されました。
和中先生は最初に、読売大賞を射止めた森上洋光さんの漢字作品を紹介。秦の始皇帝が文字統一した時に定められた「小篆」を主として用い、日々のたゆまぬ鍛錬によって鍛え上げた線質でしっかりとまとめており、「他を寄せ付けないくらい、堂々とした作品だと思います」と称えられました。
また、「小篆は筆力の鍛錬、総合的な書の学習に欠かせないのではないかと思っています。読める、読めないは別にして、漢字の作家にせよ、かなの作家にせよ、ぜひ書いてみていただきたい」と学習を薦められました。
読売準大賞の小出聖州さんの漢字作品「劉基詩」は、1970年代に発掘された馬王堆漢墓(中国・湖南省)から出土した肉筆の文字資料に普段からよく親しみ、「新出資料を手中に収めているという点で新しい感覚の書」と紹介。たとえば書き出しの「涼風」の「風」の「虫」の字が非常に簡略化して書かれており、「漢字が変遷の歴史をたどってきたことが細部に現れているのも見どころ」と説明されました。
同じく読売準大賞の井谷五雲さんの篆刻作品「飲氷亞蘭」は、「非常に躍動感があり、堂々としています。亞の字は左上に刻(ほ)り残したような塊を残しており、これが強さを表しているのも面白いと思います」と評されました。
また、読売新聞社賞に選ばれた北里朴聖さんの漢字作品「明到衡山與洞庭 若為秋月聴猿聲」を、「篆書から隷書、隷書から草書に転じていく文字自体の変化をとらえた、今までにない表現方法だと思います」とその斬新さを指摘。たとえば「若」「洞」の字の中にある「口」を、「普通は丸く書いて蓋をするところを、3つの点だけで表している」と、文字が簡略化されていく過程をそのまま表現していることに注目されました。
和中先生は、「伝統書は『読めない』『分からない』と思われがちですが、視覚的、絵画的にとらえ、迫力があるなと感じていただいてもよろしいと思います」と、書の楽しみ方をアドバイス。篆刻では「気に入った篆刻作品を縮小コピーし、ご自分の作品にちょっと貼ってみて、落款印として合うか考えてみるのも面白いと思います」と述べられました。
かな作品で色の付いた料紙が目立つ展示室では、「色紙(いろがみ)に書くのはある意味で勇気が要ることです。墨がなかなかのらない紙もありますし、かなりの筆力が必要です。私も昔、色紙を使って書いた作品を青山杉雨先生にお見せしたら『色紙はね、君、下手だということが一番分かってしまうよ』と叱られ、使い方を誤ると逆効果になることを教えられました」とユーモラスに思い出を語られました。
最後に和中先生は「われわれはやはり古典というものを、古いようで一番新しいと思っています。それが『本格の書』につながっていくということだろうと思います。自分自身も伝統に根ざしてしっかりやっていかなければと、常々思っているところです」と述べられました。
2018年8月30日(木)16:39
東京展の席上揮毫・篆刻会
東京展の開催中、8月29日午後2時から国立新美術館で席上揮毫・篆刻会が開かれました。その模様をリポートします。
一色白泉先生の司会で、最初に篆刻の和中簡堂先生が登場。会場のスクリーンに和中先生の手元が拡大して映写されると、約300人の観客は息を詰めて印刀の動きを見守りました。
和中先生は中国・北宋の詩人、蘇軾(蘇東坡)の句「風洗蒸」(風、蒸を洗う)を刻(ほ)りながら、「イメージは大体できていますが、自然な刀(とう)の動きをうまく利用して、刀の筆致というものが出るように刻っていきます」と説明されました。また、「(この石は)意外と硬いですね。師の小林斗盦(とあん)先生がよく『印材を選ぶのも実力の内だよ』と言われていました」と笑いを誘うと、「削っては刻り直すことを何時間でもやっています。大体は夜中に刻りますが、こうやっている間に夜明けになり、昼になります」と激しい制作ぶりを披露されました。
続いて今回展の審査部長、かなの黒田 賢一先生が万葉集の「時は今は春になりぬとみ雪降る遠き山辺に霞棚引く」(中臣朝臣武良自)を三尺×八尺の横作品に揮毫し、「強い線を出すために、紙の大きさに対して小ぶりの筆を使うようにしています」と説明されました。また、「線が一番ですが、白(余白)が美しくないと絶対ダメというのが信念。画家の池大雅が『描かない白を描くのに一番苦労する』ということを言ったそうですが、自分もそれを追求してきたつもりです」と語られました。さらに調和体作品として、羽生善治竜王の言葉「忘れていくというのは次に進むために大事な境地である」を淡墨で揮毫されました。
賢一先生が万葉集の「時は今は春になりぬとみ雪降る遠き山辺に霞棚引く」(中臣朝臣武良自)を三尺×八尺の横作品に揮毫し、「強い線を出すために、紙の大きさに対して小ぶりの筆を使うようにしています」と説明されました。また、「線が一番ですが、白(余白)が美しくないと絶対ダメというのが信念。画家の池大雅が『描かない白を描くのに一番苦労する』ということを言ったそうですが、自分もそれを追求してきたつもりです」と語られました。さらに調和体作品として、羽生善治竜王の言葉「忘れていくというのは次に進むために大事な境地である」を淡墨で揮毫されました。
最後に漢字の星弘道先生が登場。筆と料紙について説明されたあと、大字で「妙墨」と力強く揮毫し、昨年11月に亡くなられた篆刻の河野隆先生に作ってもらったという落款印を捺されました。さらに調和体作品として、アメリカ の詩人サミュエル・ウルマンの詩句「年を重ねただけで人は老いない 理想を失う時に初めて老いがくる」を一息に揮毫。司会の一色先生から「星先生の行書の作品には1本だけ非常に細い線があって、それが作品全体に雰囲気を持たせている気がします。意図的なものですか?」と質問されると、「ピリッとした線が1本くらい入っていた方がいいかなと思っています」と答えられていました。
の詩人サミュエル・ウルマンの詩句「年を重ねただけで人は老いない 理想を失う時に初めて老いがくる」を一息に揮毫。司会の一色先生から「星先生の行書の作品には1本だけ非常に細い線があって、それが作品全体に雰囲気を持たせている気がします。意図的なものですか?」と質問されると、「ピリッとした線が1本くらい入っていた方がいいかなと思っています」と答えられていました。
2018年8月30日(木)14:00