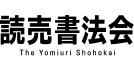2017年8月
席上揮毫・篆刻会と毛筆体験会開かれる
第34回読売書法展東京展は六本木・国立新美術館で9月3日まで開催中ですが、30日午後、国立新美術館で席上揮毫・篆刻会と外国人のための毛筆体験会が開かれました。
席上揮毫・篆刻会の会場となった国立新美術館3階講堂には約250人が詰めかけ、一色白泉先生の進行により、まず篆刻の岩村節廬先生が登場。『礼記』から「好善」を白文で彫り、さらに側款の採拓も披露されました。「丁寧すぎるよりも、思い切って彫った線の方が生き生きすると思います」などと解説する一方、「印矩の底にはサンドペーパーを貼り付けています」と制作上の工夫にも言及。会場からは「なるほど」と声があがりました。
かなでは、昨年の読売大賞受賞者の湯澤聡先生が、岸田劉生の「美とは何か 美術とは 造化の最後の そして最高の匠なるこの世界の装飾である」という言葉と、柿本人麻呂の「白たえのふじ江の浦にいさりするあまとやみらむ旅ゆくわれを」を揮毫されました。明治33年に現在の平仮名が制定される以前の仮名の多様さに触れつつ、その豊かな仮名を使って書作を行っていることを作品に即して説明。会場からは「渇筆の運筆が予想外にゆっくりで驚いた」という声が上がり、湯澤先生は「あまり速く書いては線が思うように作れません。渇筆は、墨が出るのを待ちながら書く感覚です」と答えられました。
最後は漢字の牛窪梧十先生=写真上=で、まず、北宋の詩人・蘇軾の詩「東坡」を金文でお書きになりました。金文が作られたのは3000年ほど前の時代で、その後の詩を金文で書く際、直接該当する金文文字がない場合もあります。そうした時は、漢文学者・白川静の研究などに基づいて考えられる、と説明されました。蘇軾に続いては、自作の俳句「六月雪(りくげつせつ=リーユエシエ)悲盦青闇墨勁(つよ)く」を揮毫されました。この俳句は、趙之謙(号 悲盦)、河井荃廬、西川寧(号 青闇)という師の系譜と、その師匠たちから受け継ぎ、牛窪先生宅にも植えられているという花(六月雪)をかけたもの。歴史的な流れを感じさせる牛窪先生ならではのエピソードでした。
参加者の一人は「毛筆も篆刻も採拓も、現場を見られる機会は滅多になく、楽しかったです。来てよかった」と語っていました。
外国人を対象とした「毛筆体験会」は今年の新企画です。同美術館3階研修室で、牛窪梧十先生とかなの師田久子先生が、亀澤孝幸さん、真秀ジェ-ムズさんとともに、海外出身の約30人の受講生を相手に約2時間にわたって指導されました=写真下=。受講生は「花火」「道」などの字を仕上げて生徒同士で見せ合い、歓声をあげていました。
2017年8月31日(木)15:47