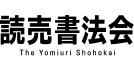2019年9月
東京展ギャラリートーク④ 牛窪梧十先生
■牛窪梧十先生(漢字) 8月26日、国立新美術館
執行役員以上の先生方の漢字作品を中心に解説されました。
牛窪先生は、古谷蒼韻先生の遺作「飲中八仙歌」(杜甫)が四枚の細長い紙に横展開で書かれていることについて、「額装になっているが、巻子の感覚で書いていらっしゃるのだと思う」と説明。「古谷先生の字の構え方は、重心が低いものが多く、ずっしり安定して見える」と特色を述べ、「1行に一文字、三文字と字数の変化もさまざまで、点(、)の(配置の)効果にしゃれっ気、遊び心が如実に出ている。普段の習練を積み重ねた上で、悠々たる境地で楽しみながら書かれているように見えます」と自在な筆運びから受ける印象を語りました。
尾崎邑鵬先生の縦作品「汧殹沔々」は、「汧」は篆書の字形、「殹」は楷書、「沔」は草書と書き分けられており、「破体書として、さり気なく四文字をまとめておられる」と指摘。また、文字数に対して紙面の幅が広いため、「上の三文字とも、偏と旁の間にたっぷり白を取って、懐の深さで紙面をおさえている。また、上の三文字とも最後に派手な線がある。それぞれの字の見せどころであり、見どころになっています」と造形上の工夫に注目しました。
 樽本樹邨先生(漢字)は右に「阮簡曠達」の四文字を大きく揮毫し、左に小さな字で謂れを記した作品=写真=。左の上半分に大きな空間が広がり、その大胆なバランスの取り方が開幕早々から来場者の注目を集めました。牛窪先生は紙からはみ出さんばかりに書かれた「阮」「達」の力強さを挙げ、「曠達(心が広く物事にこだわらない)という言葉の意味と絡めて表現されたのだと思う」と述べました。
樽本樹邨先生(漢字)は右に「阮簡曠達」の四文字を大きく揮毫し、左に小さな字で謂れを記した作品=写真=。左の上半分に大きな空間が広がり、その大胆なバランスの取り方が開幕早々から来場者の注目を集めました。牛窪先生は紙からはみ出さんばかりに書かれた「阮」「達」の力強さを挙げ、「曠達(心が広く物事にこだわらない)という言葉の意味と絡めて表現されたのだと思う」と述べました。
牛窪先生は、金文を主に書いている自身の立場から「造形的な狙いをまずしっかり決める。全体をどうまとめるか、造形上の工夫がしっかり頭の中にイメージとしていないとうまくいかない」とアドバイス。髙木聖雨先生(漢字)の作品「千變萬化」について、「『變』『萬』という複雑な字が真ん中に、単純な字が左右に来る。文字の平均化を図る考え方もあるが、ここは逆に重いものは重く、単純なものは単純に書いて変化を持たせている」と配置の計算を指摘し、「金文だが、行草のようなタッチも入っている。多様な筆遣いで現代の息吹を出そうとしたもの」と解説しました。
最後に自作を解説。「二尺×八尺の紙に、金文で40字あまりを3行で収める書き方は、今では皆さんやっている。昔を振り返ってみると、金文でそういう形式を“開拓”したのは私なのかな?と思います」と述べました。題材は、諸葛孔明の廟所に柏の木が厳かに繁った情景を詠んだ杜甫の詩。牛窪先生は3行書きの字列に「3本の木が厳かに立っているさまを書くイメージが少しありました」と説明しました。

牛窪梧十先生の作品(左)。右は角元正燦先生の作品
2019年9月2日(月)17:15
東京展ギャラリートーク③ 湯澤聡先生
■湯澤聡先生(かな) 8月26日、東京都美術館
執行役員以上の先生方の調和体作品を中心に解説されました。
湯澤先生は、漢字かな交じり書である調和体の成り立ちを説明し、「ある程度読めること、接しやすいことが一つの楽しみ」と指摘しました。しかし「読めること、読めないことが理解を左右するかと言うとそうではなく、見た印象から『柔らかく優しい雰囲気だな』『力強くていいな』と感じることでもいいと思います。私は美術館の学芸員をしていた時、『抽象絵画はよく分からない。どう見たらいいのですか?』と言われましたが、何かしら画面から感じるものを捉えれば十分だし、書もそのように見ていただきたいと思います」と述べました。

その上で、それぞれの作品を「線」の特徴に着目して鑑賞することをすすめ、「人によって心臓の鼓動や呼吸、歩くスピードも違うように、100人いれば100の種類の線がある。一枚の作品の中でも、太さ、スピード、墨量によっても線の質が違ってきます」と見どころを挙げました。また、線の流れが同時に時間の経過を感じさせることも、かな作品の魅力の一つであると説明しました。
湯澤先生は、井茂圭洞先生(かな)の作品「朧月夜」の最後尾が「夕月かかりて」「匂い淡」「し」と3行に配置され、最終行に「し」一文字だけが長く引き延ばして書かれている表現について、「この『し』に四文字、五文字を書くのと同じくらいの中身を感じます。途中でスピードが違ったりして、縦の線一本の中に味わいが集約されている。白隠(奇想の禅画で知られた江戸時代の禅僧)に一本の線を引いただけの禅画がありますが、井茂先生の作品も縦の線一本がすごくものを言っている。私も縦一本の線だけで、自分の表現したいものが書き表せたら──と思います」と述べました。
また、漢字の先生方の調和体作品も一つ一つ解説し、「私はかな作家ですが、漢字の先生方の線も参考にしています。重厚な線、渇筆、墨量の配置、グッと(紙に)入り込んだ線など、自分の好きな線があったら『今度マネしてみよう』と思いながら見ています」と、漢字作品からも常に多くを学んでいることを説明しました。
湯澤先生は「ここに並んだ先生方の漢字の作品、かなの作品も見ると、『こういう線を調和体の作品にも使ったのだな』と納得することができる。漢字、かなの古典から学んだ線や造形、ご自身が持っている表現から調和体作品を書かれていることが分かります」と述べ、執行役員以上の先生方の第1、第2作品を比較しながら鑑賞することをすすめました。
2019年9月2日(月)17:10
東京展ギャラリートーク② 中村伸夫先生
■中村伸夫先生(漢字) 8月23日、国立新美術館
執行役員以上の先生方の漢字作品を中心に解説されました。

中村先生が最初に紹介したのは、昨年8月に亡くなった古谷蒼韻先生(漢字)の遺作「飲中八仙歌」(杜甫)=写真=。「杜甫や李白の時代の『狂草』を半世紀以上にわたって学び、自分の手に入ったものとして自在に書かれたすばらしい作品」と述べました。
また、「私は北京に2年間留学したことがありますが、古谷先生に何年か前にお会いした時に書の将来を心配され、『もう一回、正しい中国の書の勉強の仕方を日本の書道界に吹き込まなければならない』と言われ、帰りの新幹線の中で私なりに期するところがありました」と振り返りました。
井茂圭洞先生(かな)が万葉集の歌を書かれた作品は、「白い紙に一本線を引くだけで意味を持ってくるが、その線をさまざまに工夫して万葉集を書かれている。同じ筆遣いがあまりないし、墨の量も違う。直球だけでなく、スライダーやフォークボールみたいな線もいっぱい出てきて、見どころ満載の作品」と述べました。
さらに、清代の鄧石如が「白を計りて黒に当てる」と述べた言葉を引き、「白によって一本の黒い線が生かされる。井茂先生は余白を『要白』とおっしゃられているが、必要な白を自分の表現の中で味方につけている」と評しました。
尾崎邑鵬先生(漢字)の「汧殹沔々」(石鼓文)は大字の縦作品。中村先生は「縦長の書の作品は、実はそんなに古いものではない。掛け軸の存在が分かっているのは南宋の終わり頃で、流行は元以降とされている」と解説し、「本来は篆書である字(石鼓文)を、行書的、あるいは楷書的な、そして一部に篆書も使って、なんとも自由な発想で作品をお書きになっている。大河に水が滔々と流れているイメージを大事にして、勇壮な表現で書かれたのだろう」と感嘆しました。
最後に中村先生は、北宋の書家・米芾の詩「寄薛郎中紹彭」の一節を読み上げました。「已矣此生為此困 有口能談手不随 誰云存心乃筆到 天工自是秘精微」(やんぬるかなこの生。これがために苦しむ。誰か言う、心を存すればすなわち筆到ると。天工おのずからこれ精微を秘す)という詩句で、「書を論ずることはたやすいが、書く手はその通りにいかない」という意味。中村先生は「私が説明したような理屈より、皆さん一人一人が筆を持って書くことの方に真実があります」と締めくくりました。

自作(左下)を解説する中村先生
2019年9月2日(月)17:05
東京展ギャラリートーク① 岩井秀樹先生
東京展の2会場で、計12回にわたり行われた東京展実行委員(常任理事)の先生方によるギャラリートーク(作品解説)を、順次リポートします。
■岩井秀樹先生(かな) 8月23日、東京都美術館
執行役員以上の先生方の調和体作品を中心に解説されました。
岩井先生はまず、漢字かな交じりの「読める書」をめざす「調和体」が生まれてきた経緯を振り返り、「まだ歴史がないため、書の作品として調和体がどういう形で成長していくか、先生方が模索をされている時期かなと思います」と現状認識を述べました。
 読売書法展に調和体部門が設けられたのは、今から24年前の第12回展。当初は読みやすさを重視して、かなの場合は「連綿をなるべく避ける」「かな作品の散らし書きのように特別広い空間を取ることを避ける」などの細かいルールが定められていました。
読売書法展に調和体部門が設けられたのは、今から24年前の第12回展。当初は読みやすさを重視して、かなの場合は「連綿をなるべく避ける」「かな作品の散らし書きのように特別広い空間を取ることを避ける」などの細かいルールが定められていました。
しかし岩井先生は、ルールが次第に簡素化されてきたのに伴い、かなの先生方の中には日頃のかな作品の雰囲気で書く傾向が表れているのではないか──との見方を示しました。
それを意識的に試みた例として挙げられたのが、高木厚人先生(かな)の調和体作品。国立新美術館に展示されたかな作品の和歌二首のうち、一首目を調和体として書いた作品で、岩井先生は「印象は『かな作品』と変わらないが、よく見ると『かな作品』にはない濁点があり、変体仮名も使われていない」と指摘しました。
また、黒田賢一先生(かな)の作品「磨(ま)すれども磷(うすろ)がず」(『論語』)に少ない文字数ながらも散らし書きの構成が感じられ、井茂圭洞先生の作品にも潤渇の使い分け、山場のつくり方など、かな作品と同じような雰囲気がある点に注目しました。
岩井先生は、かなの先生方による調和体作品には、かな特有の「散らし書き」がごく自然体で表現されていると述べ、「『散らしはどのようなものがきれいなんですか?』とよく聞かれますが、特別な定義はない。『散らしに失敗すると、“散らかし”になる。散らしの間に『か』が入っちゃったらダメなんです』としか言いようがありません」と聴衆の笑いを誘いながら説明しました。
さらに、調和体作品における題材の選び方にも話題を広げ、土橋靖子先生(かな)の作品を紹介。題材は「蜂はお花の中に お花はお庭の中に・・」で始まる童謡詩人・金子みすゞの詩で、「中に」という言葉が最終行まで8回も繰り返されています。「行書きにすると、全部下に『中に』の言葉が並んでしまう。そこで散らし(書き)にされたようです」。その結果、行間と散らしの妙に富んだ作品になっていることを指摘し、「何を書こうかと思った時、つい書きやすい題材を選んでしまうものですが、難しい題材に挑戦されている。調和体作品だからこそ挑戦できたのかもしれません」と述べました。
最後に岩井先生は、「今年はかなの先生方の調和体作品に、日頃のかな作品とあまり変わらないものが多かったと思います。かなの調和体は、これからその方向に行くのかもしれません」と改めて指摘しました。
2019年9月2日(月)17:00