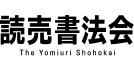お知らせ
「日展の書」シンポジウム開かれる
「改組 新 第5回日展」の開催に合わせて、「日展の書」と題するシンポジウムが、11月24日、東京・六本木の国立新美術館で開かれました。
 有岡シュン崖先生(漢字:読売書法会常任理事 シュン=「夋」に「阝」)が司会進行を務め、高木厚人先生(かな:同)、吉澤鐡之先生(漢字:同)、土井汲泉先生(漢字:同)、尾崎蒼石先生(篆刻:同)が参加した討論に、会場を埋めた約270人の聴衆が熱心に耳を傾けました。
有岡シュン崖先生(漢字:読売書法会常任理事 シュン=「夋」に「阝」)が司会進行を務め、高木厚人先生(かな:同)、吉澤鐡之先生(漢字:同)、土井汲泉先生(漢字:同)、尾崎蒼石先生(篆刻:同)が参加した討論に、会場を埋めた約270人の聴衆が熱心に耳を傾けました。
初入選の思い出
最初に日展初入選の思い出を問われた高木先生は、師匠(杉岡華邨)から手本を与えられたものの、「この通りではいけない」と少し謎めいた指導があり、字の大きさや空間の取り方に自分の創意を加えて取り組んだエピソードを披露。吉澤先生は「書家の父(吉澤鐡石)から指導らしい指導はなく、8年がかりの入選でした。遠回りした気もしますが、今になればよかったと思います」と振り返りました。
有岡先生が「結果は郵便受けで封筒を手に取った瞬間にわかるものです。落選 の通知は『陳列されないことに決定しました』という紙一枚と入場券しか入っていないので薄いのです」と経験を語ると、会場内では多くの人が苦笑いしながら頷いていました。
日展の重み
書家にとって日展は特別な目標であることが、言葉の端々から窺えました。高木先生が「展示される作品は緻密で完成度が高く、自分も破綻のない作品を作らなければ、という思いになります」と述べると、土井先生は「 日展に出す作品は集大成でもあり、同時に毎年少しでも新味を入れていきたいと思って取り組んでいます」と日展に臨む意識の高さを強調しました。
今日の課題
若者が書に関心を持たない、持ってもそれが続かない、という問題とともに、「なぜ自分の言葉で読めるように書かないのか」という識者からの指摘が紹介され、話題になりました。
吉澤先生が中学、高校での漢文教育が手薄になっていることに触れると、尾崎先生は自身の実践例を踏まえながら「小さい時に書の面白さを知ってもらう努力が必要」と子どもへのアプローチの大切さを説きました。
有岡先生は、「鑑賞者にとっては、読むのが難しく、言葉も難解で、書体もわからない。その結果、何がいいのか悪いのかもわからない、となっている面があるようです。明治・大正時代には多くの人が漢詩を素養として身につけていましたが、現在は環境が全く違います」と現状を分析しました。その上で、この問題への対応の例として今年夏に開かれた読売書法展の特別展示「読める書への挑戦」を挙げました。同展示がとりあげた調和体については、土井先生が、構築性を重んずる漢字と流動性が魅力のかなを組み合わせる難しさを指摘した上で、「少し勇気を出してこの難しさに挑戦していかなければならない」と力説しました。
日展が求める「書」とその将来像
各先生から具体的な意見や提案が出されました。
尾崎先生は「古典に立脚したものが基本」とした上で、試みとして、発泡スチロールなど新しい材料を使ったり、大きなサイズの印材で作品をつくったりすることで面白いものが生まれる可能性を指摘しました。土井先生は「書は線の芸術なので、線をどれだけ理解できるかが大事」と述べつつ、「古典を重視し、そこに少しでも新味を加えていくのが日展の将来像」と展望を示しました。
吉澤先生は、全日本漢詩連盟の会員の平均年齢が80歳である現実を紹介しながら、それでも「書の表現と意味は合致しないといけない。仮に読めなくても内容を理解して書いてもらいたい」と希望を述べ、日展の作家が高校生たちを褒賞するなど、高校生の意欲を喚起する方策についても言及しました。高木先生は「古典をベースにしたアカデミズムが日展の基本で、今後もこのままであるべき。一方、若い人たちにどう接するかは重要な課題」として、新入選作品には「新」、40歳未満の入選者には「若葉マーク」をつけたり、30歳代の入選作品を集めて展示する、という試みを提案しました。
高木先生が「日展のいいところは、変わらないスタイルがあることで、これは保持していきたいと強く思います」と述べると、有岡先生が「線の芸術という原点を見失わずに確実な伝統の継承を行い、その一方で常に新しいことを取り込むことが日展の書にとって大切」と締めくくりました。
2018年11月30日(金)17:12