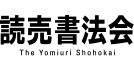連載企画「わが古典」
第六回
梅原清山先生

――青山杉雨先生に師事されるまで、どのように古典を学ばれたのでしょうか。
梅原
横浜高商(横浜高等商業学校)に在学していた19歳の頃、小学校時代の友達が競書雑誌を持ってきて入会を勧められました。私は生まれつき不器用な人間で、書道もあまり好きじゃなかったが、断り切れずに入りました。10級から始めたが、なかなか昇級しない。「もうやめる」と言ったら入会を勧めた1級の友達が手本を書いてくれ、おかげで昇級しました。それで気を取り直し、今度は一締めの半紙がたちどころになくなるくらい無我夢中で書をやり始めました。
その競書雑誌のお手本は欧陽詢の「九成宮醴泉銘」の楷書一点張りだったので、私も「九成宮」だけを勉強しました。初段に上がった時、父親に雅号を考えてもらい、「清山」を使うようになりました。しかし3段くらいまで昇段したところで、戦時下の物資不足から競書雑誌が廃刊になってしまいます。結局、書道はわずか3年ほどで途切れ、約15年間ずっとブランクが続きました。会計事務所に長く勤めましたが、一生の仕事にするのは気が進まず、書道をやっていた時が懐かしくなって、36歳の時に「書人社」という書道会を立ち上げました。
どの展覧会の審査員になってもいない、「九成宮」しか習った経験がないのに無鉄砲な話ですよ。当時は借家住まいを重ねていたので、自宅で書を教えるわけにもいかず、直筆の手本を送る通信書道を思いつきました。会計事務所に勤めていたから税務署と付き合いがある。東京国税局管内の税務署に直筆通信書道の広告を送ったら、どんどん入会申し込みが来ました。東京都区内や、横須賀・館山など十数か所の税務署に書人社会員の集団ができ、終業後に無料で教えに行くサービスも始めました。
書家としてスタートするのに、37歳ではスロー・スターターの方でしょうね。しかし、自己流の書を広めることは無責任と感じるようになり、しかるべき先生に師事して勉強し直そうと思い立ちました。書家名鑑の類を買ってきて、どの先生に師事するべきかを選び、最後に残った青山杉雨先生を訪ねました。ちょうど夏頃だったでしょうか。すると青山先生は折帖の見開きに呉昌碩の行書を臨書して、「これを来週までに書いてきてごらん」とおっしゃる。その筆づかいを見ながら「行草はああやって書くのか」と目を開かれる思いでした。帰りは電車の中でも、道を歩きながらもお手本を眺め、家で一生懸命に書いて翌週の稽古日に持って行くと、先生は「よくこんなに僕の字に似せて書けたな」とおっしゃった。そのお言葉を聞いて、本当に舞い上がるほど嬉しかった。毎回、見開きにお手本を書いていただき、とにかくものすごく練習しました。ひと月にざっと2000枚ぐらいでしょうか。
青山先生に師事して、初めて古典の大切さが分かりました。呉昌碩の臨書折帖が一冊終わった時、先生は「今日からお前に隷書を書いてやる」と「礼器碑」を臨書してくださった。「これは非常に厳格な隷書で、楷書で言えば『九成宮』みたいなものだ」とおっしゃいました。後から考えると、青山先生は医者で言えば名医だったと思います。私の体質には隷書をやらせた方が上達が早いと見て取られたのでしょう。そして礼器碑の折帖一冊が終わった時、「隷書作品を成功させるには、この礼器だけでは駄目だぞ。木簡も勉強しろよ」と今度はお手本を木簡臨の折帖に変えられました。確かに木簡に書かれた隷書を学ぶと作品をつくりやすくなる。隷書を始めてからは40歳で日展に初入選したのをはじめ、各展覧会で賞をいくつも取ることができました。
その頃から青山社中では、青山先生をはじめ篆書を書く人が結構出て来ました。やがて、私も見よう見まねで次に篆書を始めました。漢字が作られてきた過程が、象形・指事・会意・形声等の方法であることと、篆書体が文字の大先祖の姿であり、また篆書独特の曲線の筆づかいですから絵になりやすいというか、作品として引き立ちやすいと思いますね。字柄にもよりますけどね。2回の日展特選も、日展会員賞も篆書の作品です。青山先生は「篆書は『石鼓文』から始めると、時代を遡るにしても下るにしても勉強しやすい」と石鼓文のお手本をくださったのですが、その頃たまたま先生が胆石を患われたため、ご迷惑と思い、お手本をいただくのを3ページぐらいでやめて後は自分で勉強しました。その後の折帖はまったくいただいておりません。

――どのように独習されたのですか。
梅原
青山先生に師事する前に始めた「書人社」の競書雑誌に、出品課題として毎月、異なる書体の古典作品の図版を載せていました。従って、どうしても手本を書いて人に教え、添削しなければならないということになって、それが却って自分自身の稽古にもなってきたと言えますね。古典の勉強はそうやって各種幅広くやりました。行草は青山先生から教えていただいた呉昌碩が一番多く、当然、王羲之も書きました。隷書なら木簡や「礼器碑」「曹全碑」などの代表的な石碑。楷書は六朝楷書です。龍門の造像銘や墓誌銘。時には「九成宮」や褚遂良の「雁塔聖教序」もやり、結構多種類の古典に及びました。
私は最初に長く「九成宮」を勉強しただけあって、楷書には特に縁があるようです。青山先生から「お前の楷書はうまいな」と随分ほめていただきましたが、西川寧先生にも初めてご挨拶した時、「あなたはいろいろ書いているけど、楷書が一番体質に合っているじゃないか」とおっしゃっていただいた。やはり自分の体質に合っていたから、他の書体を学んでも最近はまた楷書に戻ってきたのでしょう。ただ、「九成宮」では厳密で説明的になりがちなので、野趣に富む六朝の楷書に向かったわけです。六朝楷書で日展の内閣総理大臣賞、日本藝術院賞をいただきました。
――黒澤明監督の映画「影武者」(1980年公開)のタイトルや出演者の名前を揮毫されていますが、何を意識してお書きになりましたか。
梅原
やはり六朝楷書ですね。「影武者」は最初、青山先生に依頼があったのですが、「影武者」の三文字だけでなく出演俳優の名前まで全部書くと聞いて、先生が私に話を回された。楷書は梅原なら書けると思われたのでしょう。合戦で馬に乗る俳優、歩く俳優の名前まで随分多人数の名前ですから、「千字文」ではありませんが全部で1000字ぐらいありました。時間がないから徹夜で何枚もの模造紙に書き、一枚書き上がると映画スタッフが東洋現像所に急いで持って行く。私はそれまで血圧が低かったのに、書きながらちょっと変だと思って血圧を測ってもらったら、生まれて初めて「血圧が高い」と言われました。よくひっくり返らなかったものだと思います。

――臨書はどのようになさっていたのですか。
梅原
臨書するに当たって、ただ漫然と書いているだけではいつまで経っても自分の身につきません。文字の字形を主として学んで書くのを「形臨」、筆づかいや字の雰囲気を大切に書くのを「意臨」と言いますが、手本を伏せても書けるようになる「背臨」まで行かないと本物ではない。それが自分の身についたということですから。
私はかなも随分やりました。不器用だけど、月刊の競書雑誌に課題手本を掲載している以上、何とかやらなければならないと思っているからです。今も競書雑誌に「一條摂政集」を一か月おきに載せています。なぜかと言うと、青山先生はかなも書いていらしたから。青山先生は篆隷楷行草、かなから調和体まで、ありとあらゆる書体を示されていた。自分も青山先生のようになりたいと思ってかなを勉強し続けています。
――青山先生に「よく僕の字に似せて書けたな」とほめられたとのことですが、梅原先生の字には梅原先生の個性が表れていると感じます。
梅原
個性というものは、無理に出そうと思わなくても自然に出てくるものだと思います。私は、師匠についている限り、お師匠さんそっくりに書くのがまず先決だと思っています。たとえ私が青山先生の字をそっくり書いたつもりでも、どこか違う所がある。それが個性なのではないでしょうか。いかにも偉そうに「これが自分の個性だ」と言わなくても、必ずどこかに個性的な味が滲んでいるものです。

――古典を学ぶ若い方たちに一言お願いします。
梅原
伝統芸術である書は、結局今日まで学術的に評価され、残されてきた古典が過去の先生・名人ですから、やはり古典を先生として深く学ばなければダメだということですね。その古典の勉強も、形だけの臨書ではなく、先ほど言ったように「背臨」まで進み、自分の身につけなければならない。古典を受け継ぎ、土台にして習い、そして現代の呼吸をしているものが作品になります。それからもう一つ、作品がうまいか、まずいかは、イコール、楽に書いているか、書いていないかです。一生懸命に書いても、そこに「無理のない楽な感じ」がないといけない。それが旨味です。
徹底して古典を習い、「背臨」が出来るように身に沁み込ませないと「楽」には達しません。創作作品の場合もやはり無理な感じのしない「楽」な表現が出来るまで練習することが大事です。
ただ、他人にはそう言えても、いざ私自分の作品になるとなかなか「楽」な境地までには行かない。しかしこれは結局、一番大事なことですね。

(聞き手:読売新聞東京本社事業局専門委員・高野清見/撮影 東京本社事業局・清水敏明)
※このインタビューは2018年10月18日に行いました。