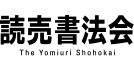連載企画「わが古典」
第五回
榎倉香邨先生

――32歳で安東聖空先生に師事し、中学教諭と18代目の宮司としてのお仕事の傍ら書に取り組まれますが、当初はどんな古典を学ばれたのでしょうか。
榎倉
安東先生の稽古日には、その当時勤めていた西脇市の中学校の仕事が午後5時頃に終わってから、神戸市垂水区にあった安東先生の家に行くと午後8時頃になりました。みんなの稽古はもう済んでいて、私が行くのを先生と奥さんが待っていて下さいました。
先生は何をせよ、とはおっしゃらないんです。手本も一切書いていただいたことがありません。作品を先生に見ていただくと、「ええやないか」と必ずおっしゃる。良かったらすぐにおっしゃいますが、ずいぶん間を置いて、考えながらおっしゃる時は良くないという時でした。その秒数を測りに行っていたようなものでした。古筆についてはよく教わりました。特に継色紙は少し意識的に見ていただいたように思います。
最初の日展特選は昭和38年ですが、その時は特選が何であるかも全く知りませんでした。びっくりして、「ああ、自分でも書が出来るんかな」と初めて思ったようなことでした。特選は2回取る必要があります。大部分の人は1年ぐらい置いて2回目を取るのですが、私は12年も間が空くんです。長い年月でしたが、私にとってはとても良い勉強の時間でした。
心配していただいたのが、安東先生の一番弟子だった西谷卯木先生です。一番最後の弟子だった私を可愛がっていただき、「紙はこれで書け、墨と筆はこれを使え」と何もかもあてがって下さいました。きっと歯がゆかったのだと思います。安東先生には書というものの厳しさ、すごさを教えてもらい、西谷先生には直接の門人でもないのに本当に身につくことを一つ一つ具体的に教えてもらった気がします。
――最初の日展特選は、関西で大字かな運動が起きた時期でした。どのような作品を書かれたのですか。
榎倉
二尺×六尺(約60cm×約180cm)に万葉集の歌一首だけでしたから、大きい字です。当時、かなの人は帖や巻子に小さな字を書くのが主で、歌一首で作品を書くようなことはしなかった時でした。私自身は別に意識したことではなく、小さい字を書くことを知らなかったんです。その頃から大字がなが主流になっていくわけですが、漢字の先生方からは「やれやれ」とけしかけられ、かなの先生方からは「そんなことをしてもしょうがない」という目で見られていました。
今でもそんなに大きな字を書く人はいませんし、書いても作品は良くないと思います。大字には瞬間的に炸裂するような美しさというものがありますが、やはりかなは綿々と続いて、時間の変化が作品に表れるのが本当だと思います。
――かなの中に時間があると意識されたのはどうしてですか。
榎倉
時間が組み込まれていないと、作品とは言えないと思います。瞬間的に音がして、びっくりさせるようなものは、また見たいという気がしないです。今から思っても、その頃の大字には書としての生命がないのではないかと思います。
書には、書き始めてから書き終わるまでの時間が必要だと思います。長い巻物や帖物だけでなく、短いものの中にも時間の長短や強弱があって、それが旅をしていくみたいに変化して最後を迎える。時間性があるものが作品としても力があります。長い時間、見る者を引きつける力が必要だと思いますから。これは漢字であろうが、かなであろうが、篆刻のようにその場所で全体を見ることのできるものも同じだと思います。

――2回目の日展特選のあと、古筆を改めて勉強されたそうですね。
榎倉
本当に古筆の勉強は何もしていませんでした。必要だとも思っていなかった。日展特選をいただいてから、古典を知らない、書けないなんて言えないでしょう。恥をかかないために陰で稽古をしました。時代を経ても朽ちない古筆の中に、日本人が求めてきた美しさというものがありありと見えてきます。たとえば「の」という字一つでも、時代によって力点が変わっていきます。いろいろな「の」があるわけですが、それには様々な条件があるわけです。
古典をやらない人が書く作品というのは、右側が書けていないんです。かなは「の」の字を連続した動きで書きますが、「の」の動きだけでは行の右側はコロコロと丸まった抵抗感のないものになります。多くの古筆ではこの右側をどう書いているかを見ることが大切です。右に小枝が出るような文字があります。また、右の行間を攪拌するような動きのものもあります。桑田笹舟先生は「右が書けたら、かなの作品は仕上がっている」とおっしゃいました。深く深く考察してみたい言葉です。
――多くの古筆を学ばれた中で、特にどの古筆がお好きですか。
榎倉
今は「一條摂政集」に取り付かれています。連綿の文字数が多いのですが、非常に自然体です。書いた人の呼吸が出ています。
「高野切第一種」のような古筆と違い、「一條摂政集」は文字が簡単でありながら一つの集団になり、流動し、動きのある面を見せています。かなは一字ずつ楷書から行書、草書になったわけではない。何行か文字をかたまりとして書こうとすると、そのために自然に省略した形になっていきます。省略すると、今度は反対に文字を寄せ合うことを要求し、集団になろうとする。そのように追いつ追われつして、次第に簡単な形になっていったのです。かたまりの要求が、省略の結果を生んだということになります。だから集団に対する美しさが見えてくると、そこには省略の姿が出来てきています。
これは書だけでなく、日本人がものを作ろうとすると、どうしても集団性というものを考えて簡単にしようとします。反対に、簡単なものにすればするほど集団が欲しくなり、一緒になろうとする。この動きは日本の彫刻にしても絵にしても、日本というものを考えていくと逃げることは出来ない大切なポイントです。あるいは文章にしても、俳句のように短い言葉で大きな世界を詠み込もうとする。それと同じように、かなの世界も大きなものを簡単な示し方で言い表していこうとします。だから、かな作品を見た時に「大きい」「広い」という気持ちが伝わってこないといけないですね。それがかなの生命だと思います。

――かな書家が漢字を学ぶ必要性もよくおっしゃっています。
榎倉
私は漢字の勉強を本格的にしていないんです。途中で「これは要るな」と必要性を感じましたが、もう間に合わない。これからかなをやる人は、漢字をしっかり勉強してほしいと思います。漢字があって、そのあとにかなが成り立つもので、最初からかなが生まれるには無理があります。
青山杉雨先生は、かなについてもよく指導していただいた先生でした。その青山先生が「六朝のかながあってもいいじゃないか」とおっしゃっいましたが、名言だと思いますね。漢字では六朝時代(中国の魏晋南北朝時代)の書をきわめて大事にしますが、その考え方がかなの中にもなければならないんじゃないかと。青山先生には、やわらかくて一見弱い表情を持つのが「かな」だという意識は全くなかったです。かなに対する考え方の一つ一つが新鮮で、先生の一言一言が刺さってくるような思いでした。
――書を語られる時、よく絵画についてもおっしゃいます。特にフォンタナがお好きだとうかがっていますが、やはり線にご関心があるのでしょうか。
榎倉
切れ味もあるし、深さもある。何もないキャンバスに切れ目を入れるのはすごく大胆なことですね。一つ切ってから、次はどこを切ろうか、というのは難しいですよ。彼の場合は一気に切ったのだと思います。切り口が盛り上がってくるようにも見え、また、奥行きを感じたり、もうフォンタナからは離れられませんね。フォンタナの作品を見るためだけに大原美術館(岡山県倉敷市)に行くこともあります。
――書と似ていますね。次はどこに、どの方向から筆を入れるか。
榎倉
やはり私は、切れ味みたいなかなの線に魅力を感じます。一方ではぼんやりとしたとか、おっとりしたとか、そういうものも書けたらいいと思うんですが、これがなかなか書けないんですよ。切っていくとか、裂いていくとか、そんな破壊的な考え方が出るのですね。
――近年は若山牧水の歌を書かれています。牧水のどこに引かれますか。
榎倉
作った美しさではなく、そのままズバリと詠んでいます。与謝野晶子の歌には割合に作った美しさが多いです。私も晶子をだいぶ長く書きましたが、牧水を書き始めてからは、もう他の歌を書こうとはしませんですね。
牧水は43年しか生きていないのですが、その間に80歳までの、100歳までもの仕事をすべて仕上げたと言うのかな、早く亡くなっても行き着くところまで行って亡くなっているのがすごいですね。恋をすることにも非常に激しく、ストレートだった。この頃は平気で書けるようになりましたけど、「死」や「恋」の字が入っている歌は書けなかったんですよ。
晩年の牧水は「静」の境地に入っていくことになりますが、激しい恋があってこそ「静」が生まれたと思うのです。何とかそういった「かな」作品を書きたいと思います。激しい表現と、静かな表現との振幅を大きく作ることが大切であると私は考えています。

(聞き手:藤本幸大・読売新聞大阪本社文化部/撮影 読売新聞社)
※このインタビューは2018年8月31日に行いました。
若山牧水没後90年記念 「榎倉香邨の書―ふるさと―」展
- 宮崎展:2019年1月11日(金)~1月20日(日) ※15日(火)休館
宮崎県立美術館
※大作32点(旧作を含む)、小品25点で構成。
12日(土)午後1時から伊藤一彦先生(歌人、若山牧水記念文学館館長)の講演会
13日(日)、14日(月・祝)午後1時~2時半、榎倉先生による席上揮毫会 - 小野展:2019年2月9日(土)~2月11日(月・祝)
兵庫県・小野市うるおい交流館エクラ
(3人のふるさとの歌人のうたも含めて)