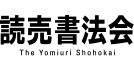連載企画「わが古典」
第四回
井茂圭洞先生

――書を学ばれる際、最初に一生懸命取り組んだ古典は何でしたか?
井茂
兵庫県立兵庫高校時代、書道部で出会った深山龍洞先生の半紙の手本を頂いたのが最初です。それは「高野切」を元にした、文字の姿の大変美しい「かな」でした。当時は「高野切」のことなどわかりませんでしたが、古筆学者の小松茂美先生によりますと、漢字からかなが出来る時は、まず漢字の楷書や行書を一字一音で読み万葉仮名や古代仮名が生まれ、その後11世紀中頃の「高野切」をもってかな書体の完成とされたとのことです。また漢字では東晋の王羲之の書や「千字文」などいろいろありました。美しい楷書は縦長なんですけれども、横に平たい宣示表風の漢字のお手本をもらいました。その頃は深山先生の専門もわかってはいませんでした。ちょうど、音楽を教える先生の専門がピアノか声楽かわからないのと同じです。その頃の私の目標が整った文字を書けることでしたから、かなと漢字を両方同時に学習していました。
京都学芸大(現・京都教育大)の書道科時代の教材で最も印象に残ったのが、「関戸本古今集」でした。昭和30年(1955年)頃は小さい帖や巻物を手本に小字から大字へと順に学ぶのがかな学習の定番でした。深山先生は私たちの頃から実験的に、大字を先に教えておられました。ちょうど書作品の陳列場所が、床の間から美術館の壁面に移る時期だったからです。かな学習には大字の古典がありませんが、先生から薦められた「関戸本古今集」はかなの大字作品になる可能性がある書風の古典でした。
――小字、大字では用筆法もそれぞれ違いますね。
井茂
深山先生は「俯仰法」でしたが、日比野五鳳先生は直筆です。青山杉雨先生、村上三島先生は筆管を持つ位置が違います。中国に「腕法に定法無し」という言葉があります。用筆法も定法無しです。本人が書きよければいい。深山先生の筆の使い方と私の使い方が特に違うのは、教育大で学んだ安達嶽南先生が直筆だったからです。深山先生は直筆を使用されることもあるものの主には俯仰法で、深山先生の師である桑田笹舟先生が設立された一楽書芸院でもだいたい俯仰法でしたので、私だけが異端児なんです。どちらがいいということではなく、自分の一番書きやすいものがいい。筋肉の働きも人それぞれ違いますしね。
「関戸本古今集」は、行頭では筆管が手前に倒れている字が多く、中頃になると筆が立ちます。例えば、側筆もあり、中頃で直筆、最後の行尾になると逆筆になることもあります。これは、弾力的な筆の毛の反発力を利用しているのです。筆が紡錘形の時にはエネルギーはありませんが、S字状になった筆の鋒先が元の紡錘形に戻ろうとする力を利用して線を引きますと、澄んだ線になります。備前焼の大家がたまには土の言うことも聞いてやれと言われたそうですが、まさに筆の言う事も聞いてやれということになります。筆圧を少しかけるとバネで跳ね返るわけです。この戻る力を私は「誘い水」と言いますが、難しいことではないのです。
――具体的にはどのような方法で古典を勉強されたのですか?
井茂
例えば、画家が景色をスケッチして帰り、アトリエで本絵を描くように、私は一つの文字でも懐素や空海ら先達の書家たちの字を字典で引いて集め、手本にしています。ただ、その通りには書きません。書家の先達の書が基になりますが、これをきっちり学んで、自分がどうするかを考えることが大事です。同じ字でも書家によってはひし形や縦型など外形もいろいろ違うので、これらを見て前後左右の関係でいつも同じ字を書いてはいけないと思うようにしています。そのためには多くの古典の字が頭に入っていないといけないわけです。画家にスケッチブックがあるのと一緒です。「万葉集」が書かれた書の古典や良寛の書など手本はあっても、その通りには書いてはいけません。
それから漢字の古典を勉強しておかないと、かなは書けません。ここに、中国・宋代の「淳化閣帖」があります。これを半紙20枚書くと2時間半かかりますが、それだけの時間をかけて学びます。その隣にあるのは米芾の「群玉堂米帖」です。こうした漢字の古典も勉強しないと大字かなは書けません。

――かなは美しさも大切な要素ですが、古典から得たことは何ですか?
井茂
私が日本藝術院賞をいただいた時、皇后陛下から、なぜ「関戸本古今集」を勉強してきたのかとのご下問を受けました。その時には「関戸本古今集はあらゆるかなの美の要素が包含されているから」とお答えしましたが、皇后陛下が、私が関戸本古今集を勉強していたことをご存じだったことに吃驚しました。
かなは「流麗の美」が一番といわれます。それに加えて「至簡の美」(簡素の美)などがあります。「流麗の美」が目立つには、間の美である「切断の美」が必要です。そして墨の美しさも大切です。「墨法の美」というのは、墨の量を紙面のある部分に集中し、強弱をつけ、平面の書を立体に見せているということです。最後は「余情の美」。かなには「散らし書き」という書法がありますが、紙面に一つの点と線が書かれることで書かれていない部分にまで緊張感が生じます。
この五つの「美」の中で、一番かならしいのは「流麗の美」です。それは連綿の美しさです。これは形の美しさで、完全な字と完全な字を足しても完全な形にはなりません。一字目に呼応して二字目を不完全な字で埋め、三、四、五文字目でその不完全さを埋めていく。四、五字と続くと五、六字目で連綿体が終わるころ行が完全に見えるわけです。これが連綿の美です。一字一字を完全に書くのはお習字で、不完全な形の字に不完全な形の字を足して、それが五、六字で完全な形になるのが、かなの一番大事なところです。全部を終止形にすると一つ一つの字が完結してしまい、他の字を寄せ付けません。これを一つの作品の中でたくさん行うとうるさく見え、目がちかちかします。適度にそれを配置しているのが「関戸本古今集」で、たくさんの美の要素が詰まった古典です。
また、「関戸本古今集」には「エンタシスの柱」の流れがあると私は思っています。ご存知のようにエンタシスの柱は下の方が膨らんでいます。見た目には貫通力があって安定感があります。法隆寺の柱もそれです。「関戸本古今集」は5割くらいはそういう行であり貫通力があります。ところが、「高野切第三種」にはそれがなく、典型的な綺麗な字ではありますが、行の下の方が膨らんではいません。
桑田先生も深山先生も、かなの美しさは連綿線にあると言われました。かな文字の組み合わせや行間の広さには「漸増・漸減の法」というのもあります。ある時は出っ張る所があり、凹むところは凹んでいる。すると、きれいに行が通るのです。これは川の流れに似ています。川の美しさは激流もあり淵もあり滝もあり、これは行間の美に似ています。
「余情の美」は、かなの世界では大変大事です。深山先生からは「余白」というのは余った「白」ではなく、必要な「白」なので「要白」と言いなさいと教わりました。その白がないと本当の美しさは出ません。「要白美」は養殖真珠の核のような働きをするもので創作意欲が燃焼し、精神の昇華が生まれるのです。
この精神の昇華について、中林梧竹先生は「梧竹堂書話」のなかで<凡そ書に法なきものは、固より論ずるに足らざるなり。法ありて法に囿せらるるものも、亦いまだ可ならざるなり。有法よりして無法に帰し、法なくして法あるは、いわゆる神にして化するもの、これを上となす>と述べておられます。こうありたいとわかっても、原稿に束縛されたのでは道半ばです。
また空海の「遍照発揮性霊集」には<書は散なり。但結裹を以て能しとするに非ず。必ず須らく心を境物に遊ばしめ、懐抱を散逸す、法を四時にとり、形を万類に象るべし。此を以て妙なりとす>とあります。
これら二つの言葉が、私の作品作りの根本にあります。つまり下書きができてもそれに拘束されてしまうと作品はできません。どんな作品を書きたいかというのはとるに足らないことであり、下書きができたからそのように書くというのはいいことではあるが、決してそれに束縛されてはならないということです。
――やはり、臨書は大事なのですね。
井茂
野球の王貞治さんも長嶋茂雄さんもスランプ対策は素振りだと言われます。小学校、中学校、高校でも素振りはしますが、高校では500回以上するのは体力作りも目的で、プロはボールが沈んだり逃げたりした時に体がどうついていくかを確認するための素振りだそうです。臨書も同じで、要らないことはせず、選んで書くということです。何を見ても書ならどうかと考えることも大事です。落語家も笑わせた後、次の話をする前に間がないといけないと。一言で笑わせるには前置きがいります。書家は24時間、書のことを考えます。ある年の日展を見て、夜行で神戸に帰るとき、深山先生は来年はこういうのを書こうと思うと、もう考えておられました。そういう話をしてくださったことが後になって大変役に立つものでした。そして先生のような充実した人生を送りたいと思い、書の道に入ったのです。
深山先生は私には「作品は似たらいかん」と常々おっしゃっていました。技術の高さのみを求めるのではなく、誰もやらなかったことをしなさいという意味です。推敲してこうなったではだめで、たとえて言うと固体が気体になるように自分の中で昇華しないといけない。計算通り書けたものはお習字です。書家にとっては、音楽で言えば頭が指揮者、手が演奏家ということで、一人二役をしています。そういうところに書道の一回性の醍醐味があると思います。人はそれに費やした年数に仕事の価値を見出しがちですが、一瞬のものにも同じ位の価値があります。ただ、見方によっては薄っぺらだと言われる可能性もありますので、そう言われないような線と表現ができないといけません。
――他にはどのような古典に取り組まれましたか?
井茂
大学に行く前に深山先生の教室に参りましたら、「4年後には君は高校の先生になるのだから、もう手本は書かない」と言われました。仕方がないので、一字ずつ独立した大字を学ぶために「十五番歌合」や「秋萩帖」なども勉強しました。そしてそれらと「関戸本古今集」で習った字を混合して、先生に添削してもらっていました。
展覧会のある時期は早くから制作に取り掛かり、先生に見て頂きました。先生は一番悪い部分を一か所だけ直してくださいますので、何回か通うと結果的に手本を頂いたことと同じになります。しかし自分で工夫して書いた後の添削はたいへん身につくことが多くありました。最初に正解の手本を与えられると模倣するだけになりますので、何回かにわたって自分の至らない点を指摘されたことが大変勉強になりました。
でも当時は若かったので、もっと変化のあるものを書きたくなりました。そこで手本にしたのが「和泉式部続集切(甲)」でした。コントラストが強く、行全体をリアス式海岸のようにしないと行に貫通力が出ません。また字間の広狭、移動連綿法、反動法、重心移動連綿法など連綿法の工夫をしました。

――長年の古典学習を踏まえ、今はどのような作品を目指されていますか?
井茂
平安朝のかなではない現代的なかなでは、可読性が重要です。しかし、それを第一義に考えると私には時間が足りません。本当は調和体のように可読性のあるものがいいのですが、今のところ自由な造形美を創造できる変体仮名は捨てきれません。ひらがなだけで私の思う作品を書くことは不可能だと思います。許される範囲で変体仮名を使いたいと思います。
「高野切第一種」に対する考えも以前とは変わりました。今はその優雅な書風とは決別したい思いです。私は漢字でも、かなでもない、今までにない美しい作品を制作したいと思っています。しかし、文字性は否定しない。つまりしっかり読もうと思えば読めるが、そのためには変体仮名を学んでいないと読めない。変体仮名は昔の人は読めましたが、今の人はひらがなとカタカナしか習っていませんので、かなも漢字も抽象画的に見てもらえればいいと考えています。

(聞き手:井上晋治・読売新聞東京本社文化部=インタビュー時は大阪本社文化部/撮影 読売新聞社)
※このインタビューは2018年5月11日に行いました。