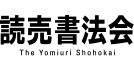連載企画「わが古典」
第二回
日比野光鳳先生

――父で、師匠が日比野五鳳という特別な家庭環境で、いかに書と向き合ってこられましたか?
日比野
私は京都御所の近くに生まれ、青年期から洛北の下鴨でずっと暮らしております。私が生まれた昭和初期は、まだまだ明治大正の延長の時代で、万年筆や鉛筆は当然ありましたが、筆で書かれた文字も至る所にありました。父は書の世界に生きた人でしたので、私たち家族も、常に書に接して暮らしてきました。私が小さい頃から、家には文部省検定の習字科試験の勉強のため、多くの中学校の先生を目指す皆さんが来られて、父から指導を受けておられた。常に書の話をし、書道の勉強をする雰囲気の中で、私は生まれ、成長しました。それもあって、私は大学では経済学を勉強したんですけど、20歳を過ぎた頃には、あらゆる書の学識に精通していました。
――どのような古典を学んでこられましたか?
日比野
私はかな書が生まれた地で、かな書の空気を吸ってきたわけです。それもあって、私の古典は「日比野五鳳」であり、「京都の空気」とも言えます。
つまり、より具体的に言えば、父が日頃から接していた漢字やかなの古典です。まず、漢字は東晋の王羲之の系統の草書、行書です。手本としては、行書は「蘭亭序」や唐代に集字された「集字聖教序」が挙げられます。
日本の書(和様)は、平安朝の「三筆」から「三蹟」へと発展しますが、元もとは王羲之の書を土台にして、日本の楷書・行書・草書は伝わりました。つまり、かな書の原点は、王羲之の書から始まっているとみていいと思います。王羲之の草書から草仮名、一般に言う変体仮名が生まれ、現代の平仮名となっていきます。
そして、かな書の古典ではまず、「古今和歌集」を書写した平安朝の「高野切」です。京都は木造家屋が多く、歴史的にみても火事がしょっちゅう起きています。だから、古典は周辺の山のふもとのお寺に収蔵されていたものが残ります。「高野切」は高野山に残ったものです。
「高野切」の中でも、「第一種」と「第三種」が有名です。日本が自らの文化を構築し始めた9世紀から10世紀、そして、それが開花した11世紀初頭の「源氏物語」の時代に、「高野切」は完成しました。特に「第一種」が、私のイメージする日本文化の完成形です。墨色の潤渇や文字の大小、自然ななかに、時折見られる変化。これらは何度見ても見事ですし、何度臨書してもそのムードを正確に再現することは出来ません。王羲之が書聖ならば、「高野切第一種」は、かな書の書聖といえます。
もうひとつは、父もバイブルとした京都・大徳寺の塔頭、寸松庵に伝来する「寸松庵色紙」です。文字の散布、つまり「散らし書き」の典型で、今日、かな書で散らし書きを考えるときに、寸松庵色紙は無視することは出来ません。かな書の古筆のもっとも上位にある品位で、「貴婦人」とも言われます。現在も私たちのグループでは寸松庵色紙を基本中の基本ととらえて、常に勉強しております。
――若い頃は、どのような書の練習をなされていたのですか?
日比野
大学を出て社会勉強をすべく、宝酒造に就職しました。そこで経理課と秘書課長をやりました。秘書課長時代の3年間は、世の中のあらゆることがようわかりました。それは現在も大きな指針となっています。
当時、社長さんは書がとてもお好きでしたから、私はほとんど毎日、当時の政財界人などに出されるお手紙などを私が毛筆で書いておりました。それが33歳から、会社を辞めて書家になる前、36歳頃までのことです。
家に帰りますと、法帖がいっぱいありましたし、筆も硯もいつもありましたから、家では毎日半紙に向かいました。当時は生活のために、小学校の生徒の書道の先生もしておりました。その頃の手本は半紙四文字です。私は約300人の子供さんを教えておりました。すると、直筆の手本が月に1200枚くらいになります。大人の方も少しずつ教えていましたから、渡す手本は全体で月に1500枚くらい。1年間では、計2万枚くらいは書いておりました。

――かな書の高みを目指す人は、どのような古典に学ぶのがよいでしょうか?
日比野
現在の日展や読売書法展では、かなりの作品が漢字とかながミックスしています。そのためには、草仮名をしっかり勉強する必要があります。漢字の楷書、行書、草書と勉強して、草仮名をしっかり勉強することが大事です。
覚えておきたいことは、学ぶ順番です。古筆学習の一番初めが「寸松庵色紙」というのはいささか無理です。中級、上級の人でなければ本当の「寸松庵色紙」や古い時代の書体がみられる「継色紙」の品格は理解できないと思います。
もう少しとっつきやすく、専門的な古典として、平安朝の「粘葉本和漢朗詠集」があります。「寸松庵色紙」や「継色紙」など、散らし書きの古筆を勉強する前に、まず、粘葉本や「高野切第三種」などで、日本的な漢字とかなの勉強をするのがよいでしょう。
「高野切」にしても「寸松庵色紙」にしても、見て書く、臨書するだけでは身につきません。臨書から、続く倣書や最終的な創作までの、長い長い道のりの中で、見る、感じる、書く、反省する、考える。という一連の動作の反復が必要です。解説書を読んでわかった気になっても、決して自分の身には付いていません。反復作業、それは時間のかかることです。
ただ、なにも一つの古筆を、毎日数十分、三年かけろとは申しません。複数の古典を平行してもいいので、自分がいいなあ、と思えるところを少しずつ書いているうちに、その好きな部分や「よい」と思えるところが不思議に増えていきます。初めは「高野切」と「寸松庵色紙」だけだったのが、三十六歌仙の1人、斎宮女御の歌集を書写した「小島切」や、古今和歌集を書写した「関戸本」もいいなと思えるようになるはずです。古典学習は自身の守備範囲を拡大するための訓練ともいえましょう。
――現代のかな書の題材では、どのようなものがありますか?
日比野
私たちの時代は、題材として万葉集、古今集、新古今集から書く場合もありました。ただ、現代は石川啄木や島木赤彦、与謝野晶子など明治以降の作家が作られた題材を書くのもよろしいと思います。題材の範囲は広いです。ただ、現代は変体仮名をできるだけ使わないで平明に表現するやり方と、変体仮名をたくさん使って劇的な作品を思考するタイプの二つに分かれます。私たちはできるだけ変体仮名を使わず、ありふれたものを使うようにしています。時代が時代だけに、人に読んで頂くこともある意味、大事です。書は文字を媒介とする芸術ですから、やはり鑑賞に来られる方には、できたら読んで頂きたい。漢字の書家は中国の唐代の作品を題材にすることもありますが、かな書家は、できるだけ現代に合わせて芸術的な作品にするように、思考した上で書くべきだろうと思います。

――これから書を学び、レベルを上げたい人の心構えや練習方法など、アドバイスをいただけますか?
日比野
文字に対する関心が大事です。少しでも字が上手に書きたいというのが日本人ですが、諦めて全然勉強しない人と、すこし勉強して上手に書きたい人がいます。いわゆる、お習字から始めて、勉強しながら作品が出来るようになれば、読売書法展のような公募展に出品することです。単に字が上手になるのではなしに、目標を持って書展に出品し、入選を重ねて特選をいただいて、委嘱作家になる。それまで数年やって、早ければ20、30年やると、書くのが楽しくなってきます。
私は30~40代の頃は1日12時間は筆を握っていました。いろんな先生はいると思いますが、毎日少しずつ勉強すること、持続して書いて、書くのが好きになることです。「好きこそものの上手なれ」で、字を書くのが好きにならないと、嫌いな人はなんぼやっても無理です。書くのが好きで勉強していくと、奥が深いと思えるようになるのです。

(聞き手 井上晋治・読売新聞大阪本社文化部/撮影 読売新聞社)
※このインタビューは2017年7月16日に行いました。