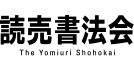連載企画「わが古典」
第一回
尾崎邑鵬先生

大阪市天王寺区の由源社にて
――これまで、どのような中国古典の学習をされてきましたか。
尾崎
最初は北魏の鄭道昭です。軍隊行く前やから、18か19歳の頃でしょう。僕の恩師の広津雲仙先生が上手でした。鄭道昭は線が曲がっています。僕は家が農家で鍬ばかり持っていたから、筆を持っても線が真っすぐできまへんで、線が震える。だから鄭道昭、鄭文公下碑というのは書きやすかった。広津先生は鄭道昭の名手やったんです。
奈良の辻本史邑先生が寧楽書道会の雑誌『書鑑』を出され、そこに鄭道昭を書かれていました。広津先生もそれを一生懸命書いて、賞にもよく入っておられた。史邑一門展にはそれで6幅くらい書いておられた。
――鄭道昭の書を学ぶときに、一番気をつけたことやコツは?
尾崎
鄭道昭は真っすぐ下には書かなくてよい字ですから、こういう字やったら手がちょっと震えても大丈夫で、震えたほうがおもしろいぐらい。それで、やりました。そしたら、戦後何年ごろか、松本芳翠先生が『書海』という雑誌を出されていて、そこに鄭道昭を書いて競書に出したら四級か何かのトップにしてくれた。それもまた自信になりました。
ところが、僕が戦後の昭和26年に京都から大阪に出てきたら、広津先生は鄭道昭じゃなしに、明代の張瑞図を書いておられる。その頃になると「張瑞図の広津」とも言われていました。黒川研水という張瑞図の名手もおられた。昭和19年か18年か、広津先生は東方書道会では張瑞図風で一席をとられた。
広津先生の張瑞図はきれいなんや。体格がよい先生でしたが、それはきれいな字です。筆を持ったら指がすーっと、ほんとにすかっと通りよる。それからは広津先生と同じ筆にしよう、持ち方も同じようにしようと思ってやってみた。でも、どうして広津先生がそうなるかさっぱりわからなかった。あとでわかったのは、先生の手が僕らよりもぐっと大きいねん。それで、これは物まねしてもあかんと思いました。
――同じようには書けないとなったとき、どうされましたか?
尾崎
広津先生の鄭道昭は、線が美しい。表面上は美しいけど生気が入らんくらいに洗練されていく。先生の弟子がみんなやっぱり華美に流れましたね。広津先生の書は美しい字肌ですが、六朝・唐代の楷法が十分に入っているので、華美でなく芯が通っている。私が張瑞図を教えて頂くと、その華美ばかりが現れて芯が通らない。辻本先生も、尾崎はそこを改めないといかんと仰り、鉄斎などの剛健な書を学ぶようご指導下さった。辻本先生の早世は私には大打撃でした。
――それを克服しようと?
尾崎
僕はどっちかというと、広津先生のようなきれいな書より、辻本先生の武骨な書き方が倣いやすかった。今も僕の鄭道昭は辻本ばりの字です。ところが、辻本先生には「おまえ、豪快に書け」って言われ、富岡鉄斎なんか教えてもらいました。辻本先生も手が大きいんで、物まねしようとしても出来ん。でも後日、大阪の酒席で鈴木翠軒先生に握手して頂いたら、先生、手が小さいんです。それで私の手も捨てたものではないと思いました。そこで、清の書画家の金農(金冬心)をやったり、富岡鉄斎をやったりしました。そういう風に自分をわかってくれる先生は、辻本先生が惜しくも62歳で亡くなられた後は、青山杉雨先生しかおられませんでしたね。
――それでその後、豪快なものをお書きになる青山先生に師事された。
尾崎
青山先生は博学でしたから、僕が行って、「倪元璐やってみんか」と言われたのは、大分しばらくしてからやったと思いますわ。ただ、明末の倪元璐は、青山先生の門下に大島嵓山先生がおって、倪元璐の名手と言われていまして、関西にも名が通っていました。
ところが、青山先生が「やってみたらどうや」って言ってくれた。東に一人、西に一人ぐらい研究者がおってもいいと思われたんでしょうな。そして教えてもらった。
東の嵓山、西の尾崎と話題にもなったらしい。ただ、関西にはそういう情報が入ってこんねん。関西では倪元璐は大島嵓山の名ばかり。それで負けてばっかりいたらおもしろくない。こっちが年齢も上やったし、負けるのはしゃらくさいと思っていました。
それでほかに何かやろうと思って、青山先生に「(明末の)董其昌なんかやろうと思いますが」って言うと、先生は「もうちょっと倪元璐やったほうがいい」って言われた。でも嵓山に負けてはしゃくにさわるから、董其昌を書きました。青山先生には、嵓山に負けてはしゃくだとは、よう言いませんでした。
――倪元璐から董其昌に移られた。
尾崎
董其昌は非常に爽やかで好きでした。そのうちに青山先生が清末の呉昌碩を書いてみろと言われて教わりました。ただ、しばらく書いていると明末清初の王鐸になってくる。青山先生に「王鐸になって困ります」と言ったら、先生は「それでいいんだ」と。つまり、呉昌碩は王鐸を師匠としてあがめとったから、呉昌碩を勉強していて王鐸になるのは、それはそれでええのやということでした。
そういうことを言って下さる先生はなかなかいないんです。「ばかやろう」「何言っとるか」って言う人が多いでしょう。青山先生は本当のことを言うてくれる先生でした。
――その後、最近はどんな古典を書かれていますか?
尾崎
曲がった字は品が出ない。だから青山先生が亡くなられた後、もう1度、楷書に戻ろうと思いました。その時に一番やったのが、北魏の龍門二十品にある馬振拝造像記です。これは近藤摂南先生がやっておられた。近藤先生は「尾崎が馬振拝をやってる」と聞いて、作品の写真を見せてくれた。それがうまく書いてますねん。だから一生懸命やりましたよ。打ち込みがこんなにきついことはなかった。
それにやっぱり隷書を入れんといかんと思って、ちょっと平たい字を書かんといかんと思っています。ここ2年ほどは、東晋の爨宝子碑と、爨龍顔碑をやっています。

――古典を選ばれる時の基本のようなものは何ですか?
尾崎
僕はやっぱり基調は王羲之やと思うんですよ。ところが、王羲之というのは研究すると、東晋の本当の字がそのまま今に来ているかどうかわからなくなってくる。やっぱり、当時の自分の好きな字に、だんだん直されたのやないかと。
例えば王羲之が「集字聖教序」のような、きれいな形の字を本当に書いたのか、ちょっとわからないですわ。それでも唐の僧・懐仁が王羲之の書を集めてつくった。集字聖教序は、僕は一番ええ手本やと思う。ありふれた字になっていくときには、王羲之の字を書いたら元に戻るんです。
――尾崎先生はどれくらい練習されていますか? 手本をどうやって自分のものにしていくのですか?
尾崎
1日に半紙に6文字ずつ、1時間書いて、約20枚くらいです。割に慎重に書いていますからね。しゃしゃっと書けへんのですよ。でも、新鮮味があるのは最初の3字ぐらいです。あとは、筆を逆に入れて、ここを曲げたほうがええのかとか、ちゃんと入れて、ぶわっとやったほうがいいかとか、あるいはまた、すうっと、筆を倒してやったほうがいいのかということを考えながら。そうやって勉強しとくと、やっぱりこうだと、何かのときにできるんですわ。
――師匠の手本をどういかしましたか?
尾崎
僕は昔は、それこそ物まねのオザキって言われてた。どうすれば先生と同じような字を書けるか。それを全部やってね。一生懸命でしたよ。
先生と同じようにしようと思ったら、以前は筆も同じ筆を使わないかんと信じていた。墨の濃さも、やっぱり濃い墨で書いとる人が、薄い墨で書いたら、その先生の味ちゅうもんは出ない。今は墨液ばっかりで書きよると思うけれど、それでいいかもしれませんけどね、僕は機械で墨をすってもらっている。
――次の世代の書家に向けてアドバイスを。
尾崎
手本がある人は、手本どおりに書いたほうがええと思います。自分の思うたことと違っても、先生の言うことを一応は聞いてほしい。僕はそう思いますわね。僕でも、倪元璐を青山先生がもうちょっとやったらどうやって言われ、もっと教えてもらったらよかったと思う。そしたら、今も倪元璐のような字を書いとると思う。
僕の場合は、やっぱり青山先生という偉い人がおって、これやってみんかと言って下さったのが一番よかったと思う。指導者も、自分の書いとる字以外のことは、やっぱりやりにくいから。その意味で、青山先生は本当に傑出していたと思いますね。やってみんかと言って、やらせてくれて、それで、勉強していったら適切なアドバイスも示して下さる。まねが出来ん。先生は偉大だった。
実は、青山先生から、「おめえな、倪元璐、あんまり弟子なんかに書かせるな」と言われたことがある。弟子のほうがうまいといかん、弟子にみんな書かせてるからあかん、これは自分のもんやって思って書かなあかん、自分のこれというものを渡したらあかん、得意技を人に渡したらいかんということです。青山先生は、いい事を言っておられます。

(聞き手 井上晋治・読売新聞大阪本社文化部/撮影 読売新聞社)
※このインタビューは2017年3月22日に行いました。