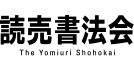連載企画「わが古典」
第三回
古谷蒼韻先生

――今日は古典学習の方法についてうかがいます。たとえば王羲之なら法帖があるわけですが、その筆遣いなどをどう研究されてきましたか?
古谷
王羲之の筆遣い、用筆法は現存している法帖からは知ることができません。王羲之の書は現在伝わっているものは全部、双鈎填墨か、拓本ですから用筆法はわかりません。筆遣いがこうとは言い切れないのです。喪乱帖も双鈎填墨です。線の命がわからないまま臨書をするのは、命が無いものを一生懸命まねするようなものです。
いわゆる臨書はあまりいたしません。ただ、やらなければいけない臨書は一通りやっています。古典学習の方法を書くよう以前月刊誌「大東書道」に頼まれた時など、一體専修より、根の広がりに心がけてと僕は書いていると思います。そういう意味では、自分で見た古典で、これは良いと思ったものは、ほとんど全部勉強しております。臨書というより、どういう書き方か、探りの勉強です。
――探りを筆でやるということですね。木簡もそうですか?
古谷
木簡は形自体がきちんとしたものではなく、好き勝手に書かれています。ですから半分斜め見をしながら、好きに書いています。僕の場合、臨模というのはありません。臨書の場合も、あまり形に拘泥しないで書いています。
――先生は良寛や本阿弥光悦など、和様にも関心を持たれています。こうしたものも先生の場合は「創造的な臨書」をなさったのですか?
古谷
手に負えないものは臨書だと思います。僕が藤原佐理で勉強したのは「頭弁帖」ですが、これは筆遣いを何とか理解しようと、一生懸命やりました。ただ、形がそっくりになることを考えない。線の動きをつかむのです。細く、遅筆でありながら、極めて安定している。それが「頭弁帖」の書法の極意だと思いました。同じ佐理でもあとの速度感のあるものはわりに書きやすく、そういうものには興味がありません。ゆっくり書いて乱れないことが大事なことだと思います。
「頭弁帖」は一番苦労しましたが、真蹟ですので勉強する価値は十分あると思います。その遅筆を取り入れて書いたのが、1968年に日展に出品した、44歳の時の作品「萬葉歌・山部赤人」です。これは殿村藍田先生と、西川寧先生とがご一緒になって、与えられる賞があれば、最高の賞をこれに与えたいとおっしゃったという記事が新聞に出ました。碑学と帖学の両方の先生にお認め頂いたのです。この頃は、遅筆で書くことに苦労していたと思います。僕は一つの展覧会毎に作風が変わります。後にもう1度書いてみましたが書けないんです。

――佐理は「離洛帖」も有名ですが、作品を自分の目で感じ取ることが古典の勉強にとって重要なのですか?
古谷
そうです。私にとって重要なのが「頭弁帖」でした。遅筆だが極めて安定している、筆遣いの最高峰です。しかも形は非常に複雑。だから渇筆になると速度が出てきますけれど、平均してゆっくり書いています。筆遣いで一番難しいところだと思います。自分で安定した速度で形をとる書き方は深みが出ません。さっと筆が走っていく感じはありますけれど、作品の奥の方に存在がある作品は、速書きではできないんです。
用筆法と執筆法は親戚関係にあります。それぞれ独立していますが親戚ですから、付かず離れずの関係です。用筆法は上下動、筆圧の問題です。非常に微妙で、簡単に体では覚えられない。実践に次ぐ実践で、書いて確かめないと口では表せません。問題は速度です。筆の横の運動ではその人なりの安定した速度があります。それよりも速い速度が別にあり、また、遅く書く、さらにゆっくりと書く…と速度は4種類に分かれ無限に変化します。この組み合わせが線になります。
執筆法とは筆の持ち方です。薬指の付け根で筆をしっかり支え、小指を内にするか外にするか。これを自分で考えます。僕はその人が自分に合った執筆法を探究しないといけないと思います。
書いた時にこうした時は良かった、こうした時は悪かったと自分の体の中で知らないといけない。ここに王羲之の法帖「南唐拓澄清堂帖」がありますが、この白い文字部分の形だけを書いても何もわかりません。そのための勉強方法として「遅・渋・速・普」の用筆法ということを思います。線が見えないと上っ面だけまねて書いてしまい、良い書家にはなれません。
――浮沈や速度など、筆の使い方が大事なのですね。
古谷
それを何も感じないで筆を動かすか、分析して白い部分に何かを感じるか、そこの違いだと思います。平成25年の時、僕は、以前から王羲之の白い所をどう書くかを探究しました。思索の塊というべきものが残っています。王右軍(王羲之)のことがそこには書いてあります。
――「頭弁帖」をそっくり臨模することはありましたか?
古谷
それはできない。それほど難解です。ぱっと見て、僕の感性で書く。だからまったく似せるという勉強はしたことがありません。45歳の「張渭詩篇」は、「日展美術」に作品を載せるから書けと、担当の青山杉雨先生から電話があり、それで懐素「自叙帖」のきついところと、鄭板橋の隷書と、正反対の所を入れて何とかならんかと思いながら書いた作品です。青山先生には割におほめ頂きました。
――そうすると、先生は目習いが大切だと?
古谷
そうですね。頭の中に書き方を残しておくということです。そこでは懐素の自叙帖が多いと思います。45歳の時の「高青邱」もそうです。杜甫「九日藍田雀氏荘」は木簡の隷書風の文字がだいぶ入っています。こう書いたらだいぶ木簡風になるなと、勘でとらえるのです。
――祝允明も学んでいますが、すっかり古谷先生の字になっていますね。
古谷
祝允明になってはいけないのです。似せてしまうだけならやめたほうがいい。学ぶ必要がない。祝允明にもふるえた字はあります。
僕は今でも、指の具合や肩の動きなど、いちいち点検しています。それも勉強です。筆が動いていて、小指一本が右上に上がるとどうなるか、これが内側に入るとどうなるか。内側に入ると薬指の根元で支え、もう少し親指が上がって、薬指の爪の付け根の所でしっかり持ち、これをあげると筆が立つ。ここで書きます。碑学系の書はここで書かないといけない。帖学系でもここが一番いいと思います。これをだいたい1日に10枚書く。なかなか固まらない時はきちっと固まるまでやります。これが私の勉強法です。

――祝允明を含めて明代頃までの古典は学ばれましたか?
古谷
筆法ではなく、気持ちで書かれた作品は勉強しようと思っています。祝允明の系統では、米芾が好きです。王羲之をやるならば米芾が早道だと思います。「蜀素帖」は若い時の書き方ですから、おそらく30~40歳代のものと思いますから、それより後の方がいいと思います。
心の動きで書の造型が変わってくるということが一番大事だと思っています。初めから造型をこうやろうと意識して、文字の形を変えるのは邪道だと思います。「唐摹王右軍家書集」という本があります。そのうちの「秋月帖」という王羲之の法帖に取り組む前に、その本で「姨母帖」を見ました。王家一族の書を見ながら、こういうものがあってこそ、これがあるのだとよく分かり勉強になりました。一方、これは「万歳通天帖」です。これも王家一族の書ですが、こういう所から、今の王羲之の書に流れてきたことを認識なさって、体内に取らないといけないと思います。
――気持ちで書く書家というと、蘇東坡はいかがでしたか?
古谷
蘇東坡は見るのは好きですが自分で書く気はありません。蘇東坡には書き癖があります。米芾の方が形に無理がなく、王羲之に近いと思います。米芾には王羲之そっくりに書こうという気持ちがあります。どちらかと言えば、割につやっぽく、艶麗な感じがします。
そっくりには書きませんでしたが、書を始めて2年くらいたった、師範学校2年生の17歳頃だったと思いますが、当時、京都博物館(現・京都国立博物館)では特別料金を出すと、真蹟を特別拝観させてくれました。僕は空海の「風信帖」を模した半紙をボール紙に貼り、家からお金をもらい、特別拝観をお願いしました。特別室で職員の方が箱に入れて風信帖を恭しく差し上げて持ってこられたので、驚いてえらいことになったと思いました。職員の方は風信帖を机に置いたあと、直立不動でじっと僕の方を見ていました。僕が真蹟を傷つけないか、対処するつもりだったんです。僕はボール紙に貼った自分の作品をこわごわ出して見比べ、ああでもないこうでもないと考えて、時を過ごし、職員の方にお礼を言って館を出ました。17歳の時だからそんな失礼なことができたと思います。
――空海は皆さん「灌頂歴名」をほめますが、先生は風信帖の方がお好きですか?
古谷
どちらもいいです。灌頂歴名は壮絶の味があり、風信帖は身を清めてお書きになったのではと思うほどの良さをねじ込めています。あの良さを取るためには相当臨書してまねしてもできないという所までやらないと得られないかもしれません。僕も学生時代はそっくりにやろうと思っていたわけです。それがなかなかそうはならなかった。僕の体質かもしれません。
――最後に、書家を志す若い皆さんにひとことお願いします。
古谷
書は、書いて体得することが大事なので、数多く書く必要があります。ただ、書くことだけでなく、書に関係のある学問に力を入れ、教養や人間性を深めることが大切です。好きな古典に数多くふれて、幅広く勉強してほしいと思います。

(聞き手:菅原教夫・読売新聞東京本社編集委員、原稿:井上晋治・読売新聞大阪本社文化部/撮影 読売新聞社)
※このインタビューは2018年1月13日に行いました。